知られざる重要作家の全貌。「没後30年 木下佳通代」(大阪中之島美術館)レポート
会場風景より、左から《'93-CA793》《'93-CA792》(ともに1993)
55歳でこの世を去った作家・木下佳通代とは
戦後、関西を拠点に活動したアーティスト、木下佳通代(きのした・かずよ、1939〜1994)の個展「没後30年 木下佳通代」が、大阪中之島美術館で開幕した。会期は5月25日〜8月18日。
木下佳通代と聞いて、知っている人はあまり多くないかもしれない。1960年代から河口龍夫、奥田善巳らの前衛美術の集団「グループ〈位〉」と活動をともにし、70年代には写真を用いた作品を中心に制作、80年代には抽象絵画へと表現の軸足を移した。1981年には彫刻家・植松奎二の紹介でドイツのハイデルベルク・クンストフェラインで個展を開催。その後も新たな展開を模索していたなか、1990年にがんの宣告を受け、惜しくも1994年に55歳の若さで亡くなっている。
生前は関西の美術界では知られた存在だったというが、早くにこの世を去ってしまったこともあり、その作品や作家像は没後、省みられる機会があまりなかった。
企画を担当した大阪中之島美術館学芸員の大下裕司は、2018年に着任した同館のコレクションにあった木下作品に興味を持ち、ほとんど知らないところからリサーチを開始。3〜4年にわたる研究成果が本展に結実した。


本展は初期の作品から代表作、そして絶筆にいたる木下の活動を一堂に紹介する。写真作品から抽象画へとその作品は大きな変化を遂げているように見えるが、大下は本展について「作家の制作に対する一貫性が伝わるものになった」と語る。
「木下はこれまで断片的、もしくは特定の作品が特異点的に紹介されることが多かった。しかし代表的な作品の裏には、チャレンジを重ねた作品や次の作品へとつながるアプローチがある。本展ではそうしたつながりを見せることで、作家の全体像を見せるものになりました」(大下)。その一貫性の根底には、木下の「存在」に対する深い関心があるという。展示を順に見ていこう。
10代から持ち続けた「存在」への関心
「1章 1960―1971」では、キャリアの初期を紹介。幼少期から絵を描くことが好きだった木下は早くから美術の道に進むことを決意し、1958年に京都市立大学美術大学に入学した。卒業した1962年には、植物をモチーフにした抽象画を描き始め、本展ではこの頃の作品から展示されている。
また大学時代に書き留めたノートからは哲学や美術教育に関する講義を熱心に受けていたことがうかがわれ、この頃からすでに「存在」というものについて哲学的・芸術的な探究を行なっていたようだ。

また木下は高校時代に出会っていた河口龍夫と1963年に結婚し、68年に袂を分つまで、河口らによる「グループ〈位〉」とともに活動していた。同グループでは「存在」をめぐる議論が重ねられており、そうしたところから受けた影響もあるようだ。ただ本展図録に掲載された1994年収録の木下のインタビューによると、15〜16歳の頃に夜空を眺めながら宇宙や自分の存在のリアリティについて思いを巡らせた思い出に触れながら、10代のときに感じた存在への関心がずっと作品のテーマであり続けていると語っているので、やはり本人にとって根源的な問いであったことは確かだろう。
また分割された立体を描いた1970年の「境界の思考」シリーズや、本展の調査で発見された71年の「滲触」シリーズには、1970年代後半の図形や線を探求した写真作品の予兆も感じられる。
理知的な思考を視覚化した写真作品
「2章 1972―1981」は、写真作品を制作の中心に据えた時期を紹介する。1972〜74年は類似したイメージに時間や状況の変化が加えられた組写真を多く手がけた。この時期、同時代の作家たちもこぞって写真を表現手法として採用しており、こうした潮流と木下も歩みをともにしていたと言えるだろう。

1976年からは、写真とカラー・フェルトペンのドローイングによるシリーズの制作を開始。これらは木下の代表的な作品群として評価されてきた。シンプルでシステマティックな作品の姿はいま見ても古びておらず、知的なクールさが感じられる。

この作品群で木下が試みているのは、実際にそこにあるものの存在と、それがいかに見えるかという認識のあいだの、同一性と差違の探求だ。
《作品 ’77-D》(1977)を見てみよう。この作品は、まず紙に2つの正円を一部重なるように描き、その紙を少し折り曲げた状態で斜め上から写真に撮る。すると、円は歪んだ形で写真に映る。その後、作家はこの写真(感光紙)の上に、改めて赤いフエルト・ペンで同様の円を2つ描くことで作品を完成させた。この写真を見るほとんどの人は、ぐにゃりと曲がった楕円状の線を見ても、これが折り曲げられて紙に描かれた正円であることをすぐに認識できるだろう。最後に加えられた赤いふたつの円が、写真上に実際に見えるかたち、紙に描かれた実際のかたち、見た人の脳内で認識されるかたちといった、それぞれのあいだのズレや一致へと鑑賞者の意識を向けさせる。

「そこに何があるか」「そこに何が見えるか」「それをどう認識するか」。こうした存在への問いと思索を、木下は作品制作を通して行っていた。
紙に図形を書いて、折って、撮影して、写真の上に線を描く。シンプルな行為だが、展示された資料からは、この図形の描き方や紙の折り方などについて作家が緻密な検討を行なっていたことがわかる。また作品に色面が登場したりインスタレーションに発展させたりと、どんどんアップデートが重ねられた様子もうかがえる。

また、前述のドイツ・ハイデルベルク・クンストフェラインでの個展ではこの時期の写真作品が展示され、木下は美術評論家の中原佑介にカタログのためのテキストを依頼している。また当時、木下は海外の美術関係者に自身の作品について紹介するための資料や手紙を送っており、こうした資料も展示されている。
本展は木下のパーソナリティや人生については展示のなかであまり言及しない姿勢をとっているが、こうした資料からは木下が作家として評価を高め、活躍の場を広げるために積極的な行動をとっていたことやその情熱が伝わってくる。
写真作品に登場していた「線」だが、木下はこの後、この線自体を描くという方向へ進んでいく。と同時に、カメラという機構を通すことで制作時にシステマティックな制限が生じる写真という制作手法に窮屈さを感じ、より自由さを感じる絵画へと回帰していく。
抽象的な絵画へ
「3章 1982―1994」は、絵画作品への移行から晩年までを紹介する。
1980〜81年にパステルを用いた表現を模索した木下だが、その後キャンバスにアクリル絵具や油彩を用いて描く絵画作品へと発展していく。
本展が記念碑的作品と位置付ける《’82-CA1》(1982)は、「描き塗りつぶす」というそれまでの手法を発展させ、画面に塗りこんだ絵具を布で拭き取ることで「カンバスの持つ平面と、絵具による色面とを等価に扱う表現に初めて辿り着いた」(本展図録、P137)という。「存在」について理知的に検証を重ねていた段階から、「存在」そのものを描きだすという転換が起きた。

絵画作品はどんどん大型化。1970年に結婚した夫・奥田善巳の作品と対をなして木下の《86-CA323》(1986)が展示された部屋を抜け、本展の終盤は圧巻。まだ新しく美しい同館の広い展示室に大型の抽象画が並ぶ様子は、海外の著名作家の個展を思わせる堂々たる様子だ。

当時木下が展示を行ったAD&Aギャラリーの空間が広かったことが大きな理由のようだが、色のグラデーション効果を使いながら、線を描き、またその線から絵具が垂れる様にも注力した作品へ。
1990年にがんの告知を受けてからは、病気の進行が進んでいたため自然療法の道を求めてロサンゼルスを訪れ、そこでも制作を行なっている。ロサンゼルスを示す「LA」がタイトルに付けられた作品群は、色彩や描き方に伸びやかさも感じられ、同地の環境からの影響もあるのかもしれない。
「描きたい、描きたいのに時間がない」。そんな葛藤を胸に、木下は病床でも作品を描き続けた。本展最後に展示された、水彩による小さな未完の絶筆。これは、絵画に回帰した1982年の第一作から数えると800点目の作品になるという。この多作さは、作家の飽くなき創作意欲や試行錯誤・アップデートを重ねて描き続けてきた探究心を何よりも物語っている。
「55年という人生の中で様々なことにトライした作家」と大下は木下を評していたが、本展はまさにそうした軌跡を辿るものとなっていた。
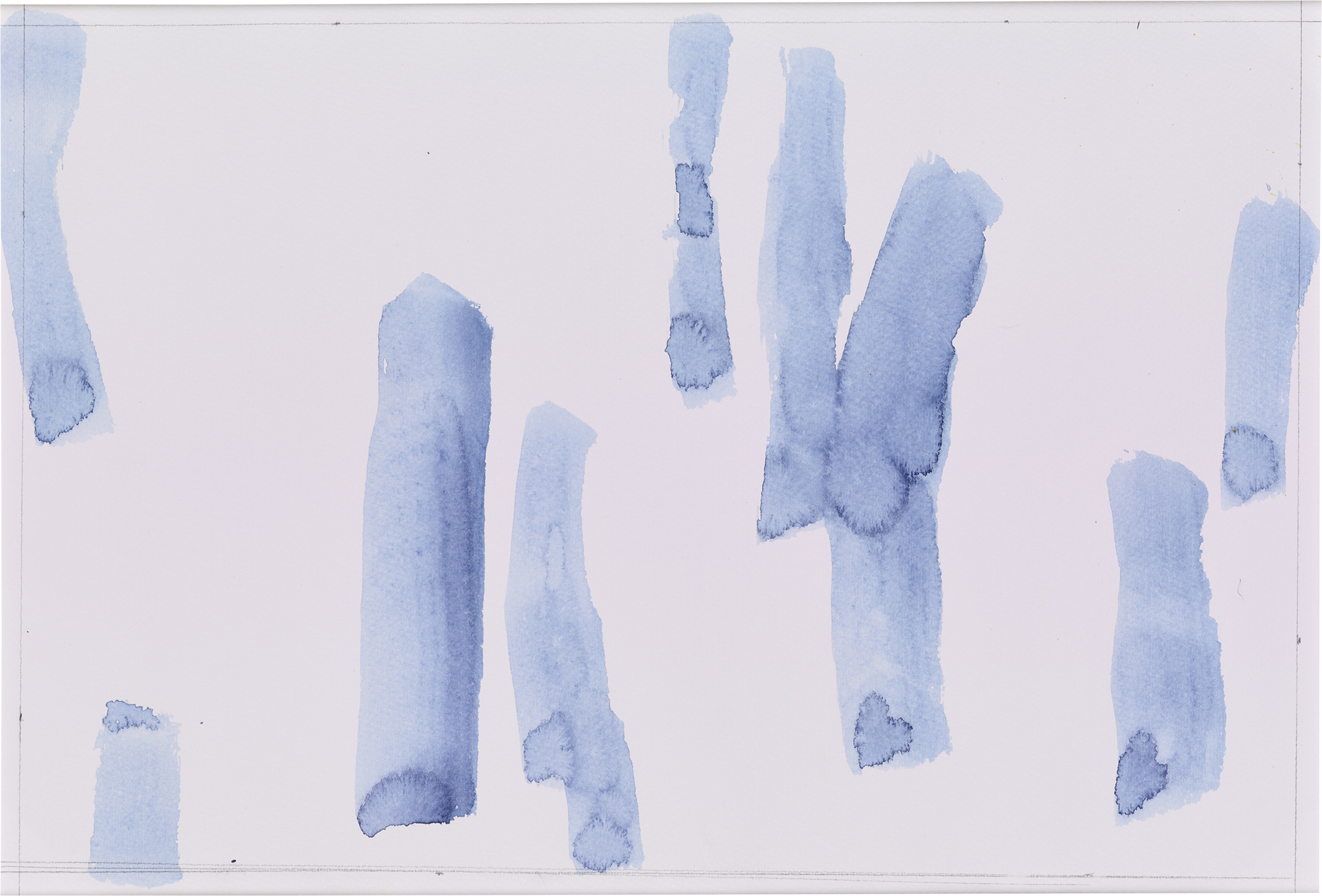
知られざる作家の再評価、美術史の見直しに向けて
また記者会見では本展について、「関西のなかで忘れ去られそうになっている作家たちの活動や闘いをきちんと評価するという意味で、今回個展を開催した」(大下)とその意図が説明された。本展はこれまで十分に知られてこなかった、木下佳通代という作家の再評価を行い、さらなる調査研究への道を開いたと言えるだろう。
こうした姿勢は、現在世界各地で進む「美術史の見直し、編み直し」「周縁化されてきた作家の再評価」という流れに沿うものであることも強調しておきたい。同館は「決定版! 女性画家たちの大阪」(2023〜24)や「大阪の日本画」(2023)といった大阪における日本画を新たな視点で紹介する展覧会を開催してきたし、関西出身ではないが女性作家という点ではアーティスト吉川静子(1934〜2019)と夫・ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン(1914〜1996)の日本初の美術館個展も今年の末から予定されている。こうした美術館の企画や展開について、今後も注目していきたい。
福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)
「Tokyo Art Beat」編集長



