ヒルマ・アフ・クリントはなぜ大芸術家になれなかったのか? 映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』レビュー(評:伊藤結希)

映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』より
私たちは美術史をアップデートできるか?
ヒルマ・アフ・クリントという名前、そして螺旋やピラミッドなどの象徴的なシンボルが淡く鮮やかな色彩のグラデーションで描かれた作品画像を目にしたことがある人も多いだろう。
それもそのはず、彼女はワシリー・カンディンスキー、カジミール・マレーヴィチ、ピート・モンドリアンよりも早く抽象絵画を描いた人物として近年知名度が高まっているスウェーデン生まれの画家だ。2018年にはグッゲンハイム美術館の回顧展で同館最多の約60万人を動員し、大きな話題を呼んだことも記憶に新しい。そんな彼女を主題にしたドキュメンタリー映画がついに日本でも公開される。

本作の興味深いところは、2000年代に入るまでほとんど無名の画家だったにもかかわらず、作家の知られざる人生を詳らかにしてゆくタイプの紋切型な美術ドキュメンタリーにはしなかった点だ。美術史が彼女を見えざる存在にしていたという明確な問題意識のもと、これからアフ・クリントの作品と出会い、語る私たちに向けた非常に同時代性の高いドキュメンタリーに仕上がっている。

なぜ女性の大芸術家は現われないのか
「なぜ女性の大芸術家は現われないのか?」。1971年に発表した論文で美術批評家のリンダ・ノックリンはこのように問いかけ、その原因が男性中心的な構造特性にあることを指摘した。ノックリンの問いには誰が「大芸術家」を決定しているのか?という問題提起も含まれるが、それもやはり男性中心で編纂された美術史という特殊な制度に負うところが大きい。
さて、アフ・クリントはどうだろうか。アフ・クリントが大芸術家として現れなかった原因はとくに作家の死後に関わっているように思う。というのも神秘主義や神智学から多大な影響を受けて独自の絵画表現を獲得した彼女は、美術界から距離を置いて活動し、存命中にはほとんど作品を発表しなかったからだ。良き理解者となることを期待したのだろうか、神智学のスター的な存在であったルドルフ・シュタイナーには作品を見せたようだが、反応は思いのほか芳しくなかった。

物質世界を超越し、精神的なヴィジョンを描きだすアフ・クリントの作品は、いまを生きる私たちが見ても驚異的な現代性を感じるのだから無理もない。思わず畏敬の念を抱いてしまう高さ3m幅の巨大な抽象絵画シリーズ《The Ten Largest》をアフ・クリントが描き始めたのは1907年のこと。日本では黒田清輝、浅井忠、岡田三郎助らが審査員を務めた第一回文展(明治40)が開催された年だと思えば彼女の特異性をより実感を持って理解できるのではないだろうか。だからこそアフ・クリントは死後20年間作品の公表を禁じ、自身の作品を理解してくれるであろう未来の人々に託したのだ。
奇しくも彼女はカンディンスキー、モンドリアンと同年の1944年に亡くなる。しかしながら、託したはずの未来の人々の対応は予想に反して冷たいものだった。70年にアフ・クリントの甥の子がストックホルム近代美術館に作品を寄贈しようとしたところ、霊媒師の作品に興味はないと軽くあしらわれてしまうのだ。

カンディンスキー、マレーヴィチといったいわゆる抽象絵画のパイオニアたちも程度の差はあれ神智学に影響を受けているが、アフ・クリントのように交霊会で精霊に依頼されてオートマティスム的に制作した絵画作品というのはなかった。ストックホルム近代美術館にとって既存の美術史に適合しないアフ・クリントの出現が不都合だったことは想像に難くない。
彼女の作品を収蔵するなら抽象芸術への言及は避けては通れないし、そんなことをすれば美術史を書き換えることになってしまうからだ。だからこそ当時の人々は骨の折れるような作業をするよりも、アフ・クリントを美術史のフィールドから周縁化することを選択した。
アフ・クリントがなぜ大芸術家として現れなかったのか。それはかねてより白人男性中心主義的な視点で芸術を論じてきた美術史という制度の問題であり、ひいてはその美術史をなぞりながら作品を見る(美術史を再生産する)私たちの問題なのだ。
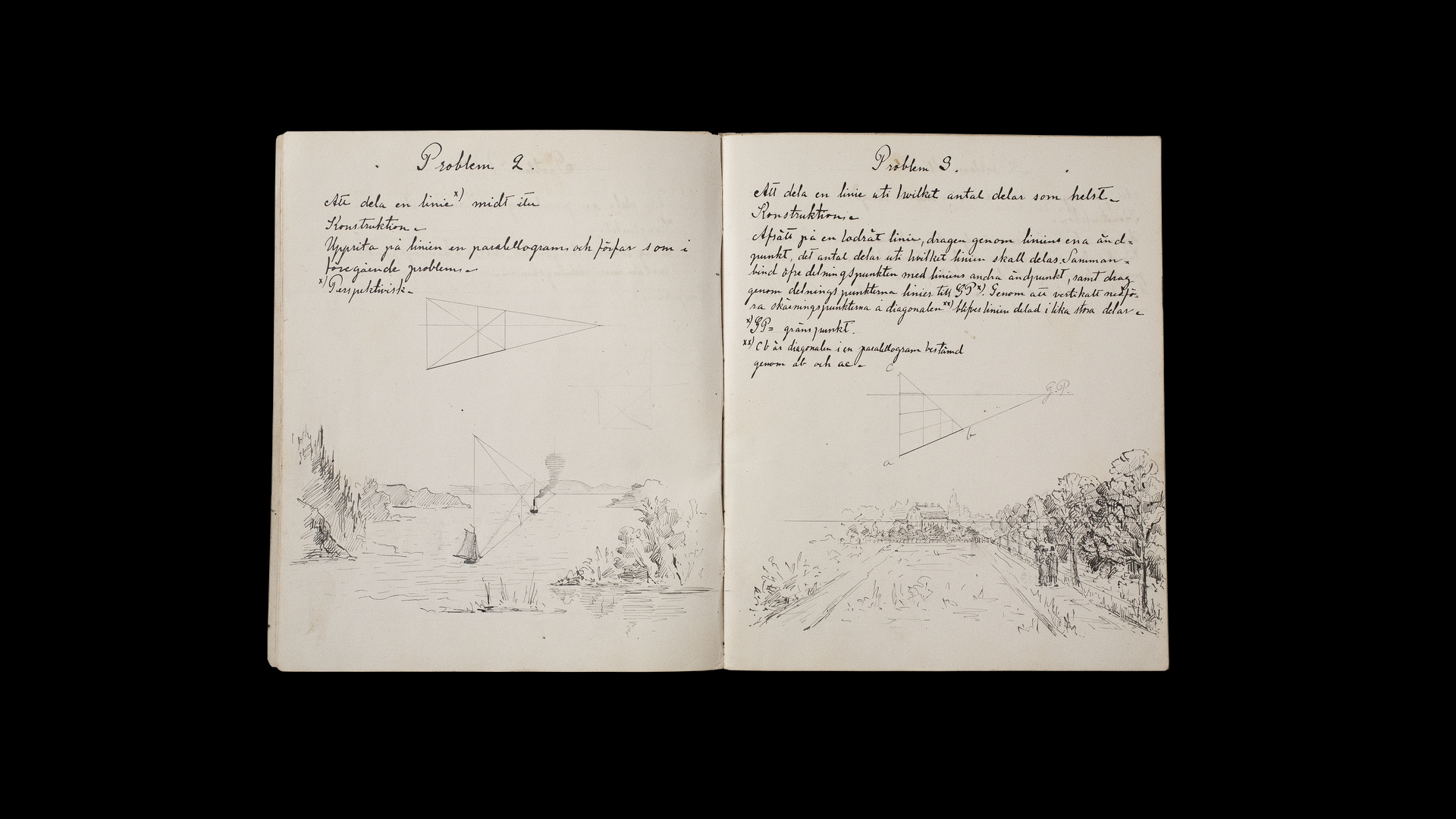
美術史のアップデートによって開かれる未来
アフ・クリントを美術史上に位置づけるには、既存の美術史にアフ・クリントを補遺として加えるのではなく、美術史そのものをアップデートする必要があるだろう。しかしながら本作でも言及されているように、どうやらニューヨーク近代美術館(MoMA)は彼女の作品を抽象芸術といえるか判断しかねているらしい(*1)。
MoMAと抽象芸術といえば、初代館長アルフレッド・バー・Jrが「キュビスムと抽象芸術(Cubism and Abstract Art)」展(1936)で掲出したダイアグラムが有名である。そこでは新印象主義から始まりキュビスムを経て、未来派、ダダ、構成主義といったあらゆる運動が抽象芸術に収斂する進歩史観的な美術史が語られている。
2012年に同館で開催された「抽象を発明すること1910–1925 (Inventing Abstraction, 1910–1925)」展ではヴァネッサ・ベル、ヘレン・サンダース、ナタリア・ゴンチャロワといった女性作家を付け加える若干の見直しが行われるが、カンディンスキーが抽象絵画を初めて描いたとされる1910年を起点にしていることからも明らかなように、基本的な図式は36年版を継承している(*2)。それどころか本展で新たに作成した作家のネットワーク図は、バーの思想をより一層強化しているようにさえ思える。
こうした抽象芸術をとりまく保守的な美術史にメスを入れたのが、昨年ポンピドゥー・センターで開催されたばかりの「彼女たちは抽象芸術をつくる(Elles font l’abstraction)」展(2021)だ。1860〜1980年代という時代の幅をもたせながら、マルチカルチュラルな視点で110人近い女性作家を取り上げて抽象芸術の歴史を読み直したじつに意欲的な企画である。ここでアフ・クリントはジョージアナ・ホートン、アリス・エシントン・ネルソンといったスピリチュアリズムに接近し超自然的な方法で抽象画を制作した作家や、エマ・クンツ、オルガ・フレーベ・カプタインのようなスピリチュアルな体験を探究する過程で抽象画を生み出した作家とともに紹介された。
注意しておきたいのは、カンディンスキー以前の彼女たちは自らの作品を抽象画とは呼んでいなかったということ。そして絵画を純粋な造形要素に還元するといった芸術上の目的で抽象的な表現に辿り着いたのではないということだ。それでも「彼女たちは抽象芸術をつくる」展は、未だ見慣れぬ作品ついて既存の価値観から抽象芸術か否かという二者択一の審判を下すのではなく、抽象芸術の枠組みそのものを拡大した。このように美術史をアップデートすることは、文字通りの意味で美術の可能性を広げてくれる。
本作は2019年に制作された映画であるから、この素晴らしい兆候を登場人物たちはまだ知らない。近年はフェミニズムを追い風として美術館の収蔵品や展示でジェンダー不平等を是正する動きや、偉大なアーティストの陰に隠れて過小評価されていた作家を再評価する気運が確実に高まっているが、そうした再発掘の作業と並行して、現代の視点から現代の精神を反映して歴史をアップデートしていくことも重要だ。歴史の記述は一度筆を擱いたら終わりではない。何度でも筆を持ち直して良いし、筆を持って意味や価値を創出することができるのは現代を生きる私たちなのだから。アフ・クリントの作品が並ぶ美術史は豊かでずっと面白いものになるだろう。

*1──アフ・クリントの作品が初めて美術史の文脈で紹介されたのは1986年にロサンゼルス・カウンティ美術館で開催された「芸術における精神的なもの:抽象絵画1890-1985(The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985)」展だった。しかしカンディンスキー、マレーヴィチ、モンドリアンといったスターと並んで展示されるのではなく、単独で一部屋での展示だった。展示方法からも当時のキュレーターたちがアフ・クリントの扱いに困惑していたことが伺える。Thomas McEvilley, “The Opposite of Emptiness,” Artforum, March 1987, vol.25, no.7.(リンク)
*2──映画にも登場した美術評論家のユリア・フォスは、カタログ本文は言うに及ばず注釈にさえアフ・クリントが登場しないMoMAの旧態依然とした美術史観を指摘している。Julia Voss, “Hilma af Klint and Evolution Art,” in Hilma af Klint Painting the Unseen, exh. cat., London: Koenig Books, 2016, p.23.
『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』
監督:ハリナ・ディルシュカ
出演:イーリス・ミュラー=ヴェスターマン、ユリア・フォス、ジョシュア・マケルヘニー、ヨハン・アフ・クリント、エルンスト・ペーター・フィッシャー、アンナ・マリア・ベルニッツ
2019/ドイツ/94分/英語、ドイツ語、スウェーデン語
英題:Beyond the Visible – Hilma af Klint
配給:トレノバ
後援:スウェーデン大使館
2022年4月9日より、ユーロスペースほか全国順次ロードショー
https://trenova.jp/hilma/









































