美術館はアーカイヴの困難さとどう向き合い、活用しているのか? 「国立アートリサーチセンター国際シンポジウム・ワークショップ2023」レポート #1
会場風景 撮影:仙石健(.new)
⽇本における新たなアート振興の拠点として、「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに掲げる国立アートリサーチセンター(NCAR)は、2024年3月22日、国際シンポジウム「美術館とリサーチ|アートを“深める”とは?」を国立新美術館(東京・乃木坂)で開催した。
このシンポジウムに先駆け、21〜22日にはキュレーターやアーティスト、研究者ら有識者による4つのセッションを開催(一般非公開)。今回Tokyo Art Beatでは、この4つのセッションとシンポジウムのレポートを全5回でお届けする。
本稿では、3月21日に開催されたセッション1「美術館とアーカイブ」をレポート。前半は国内外の美術館に所属するそれぞれが、作品収集や展示、資料アーカイブの実践例を紹介し課題を提起した。後半では、寄贈作品の受け入れの難しさに共感の声が交わされたいっぽうで、アーカイブの活用にまつわる議論や事例にも話が及んだ。
◎パネリスト
原舞⼦(三重県⽴美術館 学芸員)
ダニエル・ムジチュク(ウッチ美術館 近代美術部⾨⻑)
江上ゆか(兵庫県⽴美術館 学芸員)
◎モデレーター
光⽥由⾥(多摩美術⼤学アートアーカイヴセンター 所⻑)
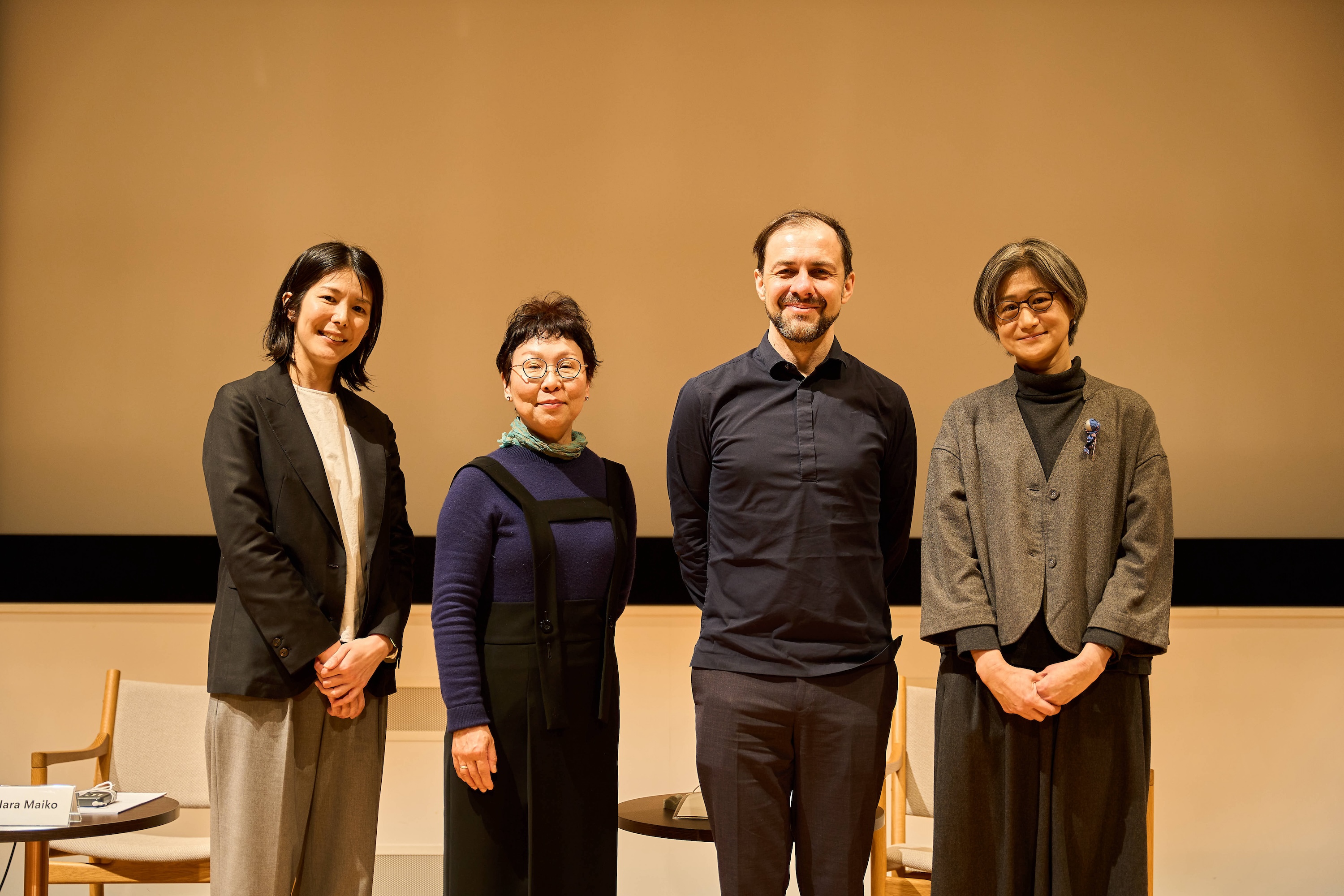
原舞子:秋岡美帆の作品寄贈と展示活用
三重県立美術館学芸員の原は、後半生を三重県で過ごし、2018年65歳で急逝した現代美術作家の秋岡美帆の事例を紹介した。同館では、作家の遺族から相談を受け、遺された100点を超える作品の整理と調査を実施。そのデータをもとに約40点の作品が、秋岡にゆかりのある全国のミュージアム13ヶ所へ収蔵されるに至った(2024年3月時点)。
同館はその後、秋岡の三回忌にあたる2020年春にコレクション群を一挙公開する特集展示を開催し、作品を所蔵した愛知県美術館でも、2020年秋に特集展示を開催。作品の展示や保管、額装に関して他館からの問い合わせに答えるなど、情報共有がなされることもあったという。

これらのことから以下の2点がポイントとして挙がった。
1. 作家本人や作家と協業したことのある学芸員がいなくなった後も対応できるよう、作品や展示に関する情報共有が可能なネットワークづくりが重要。ミュージアムは来館者だけではなく学芸員にとっても開かれた場であること、どこからでも情報にアクセスできることは大切。
2. 地方自治体の美術館が地元作家に果たす役割は大きい。一人の作家の作品をまとめて一つのミュージアムでコレクションすることも大切だが、各地の館へ分散させ、共同で所蔵し展示するという構造は、今後の研究や展示においても有益な仕組みでは。そのためにはハブとなる館の存在が重要。

ダニエル・ムジチュク:社会主義体制下でのアーカイヴと再現展示の試み
ポーランド共和国第二の都市・ウッチにあるポーランド国立ウッチ美術館(Muzeum Sztuki)は、中央ヨーロッパや東ヨーロッパを中心とした前衛芸術の歴史を中心に、近現代美術を扱うミュージアムだ。
第二次世界大戦後、ソ連の影響下に置かれ社会主義体制となり、大半の抽象画は展示が禁止された時期もあった。破壊されてしまった作品の再現展示は、作品が制作された当時の記録写真などのアーカイヴ資料を活用し、1960年代から取り組んでいたという。同館近現代美術部門長のムジチュクは、アートへのアプローチにおいてつねにアーカイヴを活用することが大切、と述べた。

また、日本の戦後美術と同館との知られざる影響やつながりの可能性にも言及。海外旅行が珍しかった1960年代半ば、美術評論家の中原佑介(1931~2011)が初めての渡航先としてポーランドを選び、それが中原にとって抽象美術にふれる機会につながったことや、同館の館長を務めたスタニスワフスキーが度々来日し、日本の美術をヨーロッパへ巡回する際も、会場を提供するなどの交流が生まれていたと明かした。

江上ゆか:関西圏の現代美術と「信濃橋画廊」のアーカイヴ
1970年開館の兵庫県立近代美術館を前身とする兵庫県立美術館は、1995年の阪神淡路大震災を経て、2002年、現在の場所と名称で、創造的復興のシンボルとしてリニューアルオープンした。併設された美術情報センター(美術図書室)は、関西圏で有数の規模を持ち、12万件もの蔵書・資料が閲覧できるという。

同館学芸員の江上が事例として紹介したのは、1960年代から2010年まで、大阪で活動していた現代美術の貸し画廊「信濃橋画廊」資料の調査と整理についてだ。画廊オーナーから作品とともに寄贈された展覧会DMや芳名帳などは約3900件にのぼるという。これらを活用し、同館では展示写真や作家インタビューなどとも連動させた「信濃橋画廊コレクション」展を開催。とくに当時の関係者への聞き取りは「日常的であたりまえだからこそ記録に残されていないことを残す取り組みだった」という。
また、旧館時代より紙資料を保管する「作家ファイル」の運用やあり方についても紹介。そして、所蔵品を有する美術館としては、わざわざ書き残されることはないがディテールのリアリティを立ち上げるには不可欠な、作品をめぐる「非常に個人的な一般鑑賞者の経験」をどのように記録に残しうるかが、大きな課題であるとも語った。
ディスカッション
参加者からの質問に答えながらのトークとなった後半。日本とイギリスの美術大学で教えた経験を持つ参加者が、美術史を学ぶ学生ですら、デジタルでのリサーチに留まり、図書館で資料にあたることなどを避ける者が少なくない現状にふれ、アーカイヴの活用方法や面白さやをどのように伝えているのか、問いかけた。

モデレーターの光田は、多摩美術大学のアートアーカイヴセンター所⻑でもある自身の経験をふまえ、「現代の学生らは、たとえばマルセル・デュシャンから始まる歴史の一環に自分の作品があるという意識や、他者の作品と自分との関係性を思考する経験が希薄かもしれない」と指摘。同館がコレクションする、詩人・美術評論家の瀧口修造(1903~1979)旧蔵のアーティストブックを見せるなど、ウェブ上で見るだけではない、情報として流れていってしまうものを『体験』にすることも試みている」と明かした。
江上は、ゲームやアニメーションを学ぶ大学生らに授業を行った際、80年代に作家活動をしていた若者らを取り巻くアートのインフラや、画廊をどのように利用して作品を発表していたか、について学生が非常に高い関心を示したことを挙げ、「いかに利用者の関心事にアーカイヴを紐づけ、提示できるかの工夫が必要だろう」と述べた。

また、別の質問者から、「アーカイヴからこぼれ落ちてしまうものを鑑賞者へ伝えるにはどんなことができるか、またキュレーターはどんな役割を担えるだろうか」という、現場ならではの声も挙がった。
ムジチュクは、戦争と社会主義に分断され、表現が抑圧された時代に、いわばアーカイヴの空白期間が生じたことにふれ、その後1950年代には、アーティスト自身からの提案で、残った資料をもとに1930年代の絵画を50年代に再制作した取り組みを紹介。「再制作はオリジナルをすべて内包する」という言葉も印象的だった。
江上は、1980年代の関西若手作家らの作品は売れることがほぼなく、市内の美術大学では打ち捨てられた作品がいくつもあったことにふれた。そして「現代美術の作品、とくにインスタレーション作品などは、展示のプロセスそのものがアーカイヴされ、開かれた情報としてアクセスできるようなキュレーターの取り組みが大切」と述べた。

参加者それぞれの業務と環境、活動の背景や事情は異なれど、紹介された事例はいずれも各館のスタンスを示しており興味深く、2時間半におよぶセッションは終了時刻ぎりぎりまでディスカッションが展開される、充実した内容だった。
*「国立アートリサーチセンター国際シンポジウム・ワークショップ2023」ほかの記事はこちら
Naomi
Naomi



