Media Practice 08-09
東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻の生徒たちが、寝る間も惜しんで制作した作品たちを発表する場である、今回の展覧会。横浜、馬車道駅から歩いて数分のところに位置する、横浜トリエンナーレでの盛り上がりも記憶に新しい、BankART Studio NYKにて現在開催されている。コンクリート打ちっぱなしの場内。その広大な面積と天井の高さを効果的に利用したインスタレーション。薄暗い中にいくつも浮かび上がる大小のスクリーンが、訪問者を建物の奥へ、奥へと導いていく。
「映像」と聞いてまず思い浮かべるのは、何かしら視覚に訴える作品であろう。観る側が、画面に映し出されたイメージと正面から対峙する形式をとった作品。そんなものを想像される方が多いのではないだろうか。無論、本展で発表されている作品の多くには、コンピューターやテレビなどの小型スクリーン、映画上映用の大型スクリーン、そしてカメラやプロジェクターなど、映像を映し出すための装置がふんだんに使われていた。そんな中にも今までにない新しさ、映像の新たな可能性を実感することが出来たのは、それらの装置と観る側の関係性が、従来のものから更に一歩踏み込んだものだったからであろう。つまり、画面上の映像を受け身の状態で観るという既存の展示方法を超えた、観客を完全に巻き込むことで初めて成立する作品が、そこには数多く存在していたのだ。

池田さんはまず、波の映像をビデオ撮りし、それを各フレームごとに分解することで、あの膨大な数のイメージを起こしたのであろう。通常の映像の場合、1秒間に24フレームあるが、それをおそらく倍ぐらいに引き伸し、1秒間分の映像が何十フレームにも分割されている。これをまた映像として流せば、スローモーション中のスローモーション、つまり”slowest”になる。そして、このような手間と時間をかけることで到達したのが、ただ波の映像を一方的に流すだけでは終わらない、鑑賞者が”手に取って”眺めることが出来る作品なのだ。

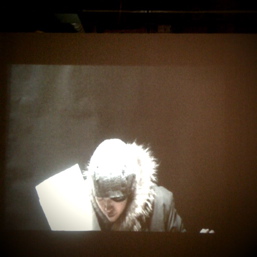
何も映っていない大型スクリーンの前に身を置き、「・・・?調整中なのだろうか」と一瞬戸惑ってしまったのが、田村友一郎さんの《Coney Island》。暫くそこに立っていると、突然スクリーン上に現れた友人のクローズアップショット。驚いて周りを見回すが彼の姿はどこにも見えない。暫くうろついた末、やっとからくりが明らかになった。スクリーンの真裏に位置するスペースに真っ直ぐに積み上げられた木箱。その内側からは微かな光が滲み出ている。そこに隣接する形で、やはり木箱を積み上げて出来た階段が設置されており、友人はその最上段まで登って、木箱の中を覗き込んでいる。なるほど、その木箱の中にカメラが仕込まれていて、覗き込んでいる彼自身が気付かぬ間に、その顔が前方に設置されたスクリーンに映っていたのだ。
しかし、木箱はスクリーンの裏に位置しているため、映っている本人は自分自身の姿を観ることが出来ない。観る側が気付かぬうちに作品の一部になり、そしてそれを完成させるという発想の面白さ。更に、映し出された自分の姿を同時に観ることが出来ないもどかしさもいい。映像というメディアを媒体に、作品と鑑賞者の新たな関係を築いた、新鮮な驚きを与えてくれる作品だ。私も友人に続いて階段をゆっくりと上がり、木箱の中を覗いてみた。そこには予想通り、カメラらしき小型装置が設置されていた。そして、そこにもう一つ隠されていた、予期しなかった驚き。これは観てのお楽しみ、ということにしておこう。



作品タイトルでも紹介されている内田光画子という日本人女性が、19世紀末を横浜で生き、彼女が自らの身体などをレイヨグラフという手法で撮影するようになったらしい、というのがストーリーの始まりである。そこから、光画子の人生、そしてこの独特な撮影技法を編み出すまでの経緯等が語られる。ビデオの中で取材を受けているのは、光画子について研究を重ねている写真史家のアメリカ人男性。彼が、光画子の父親が横浜で経営していたという写真館の住所を突き止め、そこを訪ねる場面や、光画子の写真家としての人生を語る場面で、ビデオ作品は綴られている。

様々な方向から映像という媒体を考察し、それを大胆に駆使した作品に出会えた本展。若い世代のバイタリティと柔軟性がひしめいている、そんな印象を受けた。もう一つ魅力なのが、展示会場に滞在している(何日間にも渉って泊まり込みの作業をしている生徒さんも多数だという)作家たちと、彼等の作品を前に自由に言葉を交わせるという点である。我が子のように愛おしい自分の作品について、詳細に、そして熱く語ってくれるのが嬉しい。そういう意味でも、鑑賞者と作品がぐっと近づける、究極の参加型展覧会であると言えよう。1月25日(日)まで開催の本展。この週末、横浜まで足を運んでみてはいかがか。



