李傑(リー・キット)「The voice behind me」レビュー
資生堂ギャラリーでは、7月26日(日)まで、香港出身のアーティスト、リー・キットの展覧会が開催されている。リー・キットは、2013年にヴェネツィア・ビエンナーレに香港代表として参加し、「ビエンナーレ必見アーティストベスト5」に選ばれ、世界中から注目を集めた。
リー・キットにとって、絵画は呼吸と同じことだという。
「そこに存在しなくても、その人の呼吸を感じることができるということ」。
“つまり、絵が上手いから画家なのではなく、展示が良いからでもなく、その画家の行為によって人々が彼の展覧会や作品の存在を感じるからこそ、その人は画家なのです。私にとって、これは呼吸と同じことです。そこに人がいなくても、その人の呼吸を感じることができる。それが真に存在しているということです。”(第55回ヴェネツィアビエンナーレ香港パヴィリオン個展『You (you).』カタログより抜粋)

その言葉が示すとおり、リーの作品は、ペインティングや映像、レディメイドオブジェクト(既製品)などを組み合わせることで、展示空間全体が一つの絵画のようになった作品だといえる。
そして、それらが生み出す風合い、光、色……など、言葉にできない感覚によって、まるでさっきまでそこに誰かがいたかのような雰囲気を醸し出しているのが特徴だ。
リーは、「”絵とはそもそも何なのか?” “アートの意味は?”と聞かれることがあるけれど、それを論じること自体は無意味」と言い放つ。
「それは、男/女である意味は?と聞くことがナンセンスなのと同じことだよ。」
絵画というより一つの雰囲気を作りたいと思っている。展覧会が終われば、展示品はレディ・メイド・オブジェクトになる。同時に、アート・ヒストリーもレディ・メイド・オブジェクトになる。展覧会で作品を展示することは、いわばコーヒーフィルターのような役割を果たすのだと、リーは言う。
今回の資生堂ギャラリーでは、リーの過去の代表作と新作とを組み合わせてリーの世界観に迫る展示となっているが、ここでまずは、過去の代表的な作品をいくつか紹介してみたい。
■ピクニックの布
リー・キットが注目を集めるきっかけとなった初期作品の一つに、絵の具でストライプや格子柄などを描いた布のシリーズがある。この作品を作り始めた当時、香港の美大生だったリーは、日々布にペイントしては洗い、またペイントしては洗ってと、同じ行為を繰り返していた。
学校で、「これは抽象画か?」と聞かれれば、「はい。柄と色があるので、抽象画です。」と言えばよかったし、「具象画?」と聞かれれば、「はい、これはテーブルクロス(という機能を持ったもの)なので具象です。」と答えればよかったので、”便利”な作品でもあったという。
こんなところにも、作品全体に通じるリーらしいウィットの一端が窺えるのだが、当初は、日記を書くのと同じように個人的な行為として行っていて、木枠にマウントして絵画として発表することをは考えていなかったという。
それがやがて、ペイントした布をテーブルクロスやタオル、シーツ、カーテンなどとして日常生活の中で実際に使用し、日々の生活の痕跡、誰かの面影や思い出をまとうことで、作品として完成していった。
■『カードボード・ペインティング』シリーズ
また、リーの作品に多く登場する題材に、淡いパステルカラーに彩色された段ボールに、ニベア(Nivea)などの日用生活用品のロゴをペイントしたシリーズがある。
もともとは幼い頃におもちゃよりもニベアの缶入りクリームに強い愛着を感じていたというリー自身の個人的な経験に由来しているのだが、これら世界的に広く行き渡ったブランド名は、観る側の多くにもそれぞれの個人的な体験を呼び覚ます。
リーは、毎日の生活の中で何度も目にする製品に特定の人物への感情を重ねる癖があり、次第にこれらの商品ブランドに、その人物に対するのと同じような親近感を覚えるようになるのだという。
「たとえば、メアリーという人物のことを強く考えているとき、シャワーの中で使う製品名に、次第にメアリーのイメージが重なってくるんだ。」
このような感情は、特に、香港のような密集した都市で生活していることも大きく関係していて、シャワージェルといった日常品にさえ親密な感情を抱くようになるという。
こうして、リーの作品は、日常生活の中に密接に取り込まれることで思い出や記憶と結びつき、より親近感を帯びたモノとして存在感を放つようになる。
リーの作品には、他にも、折りたたんだ布、タオル、タオル掛け、クッションといった生活に根ざしたアイテムがよく登場する。一見無造作に配置されているように見えるのだが、一度でも彼の作品を目にしたことがある者には、それがリーの作品だとすぐに分かる。作品の配置については、厳密に考えているところもあるが、最終的には偶然を重視し、感覚で決めているという。
「すべてがコントロールされていたら、世の中面白くなくなるでしょう?」
と、語るリーの目には茶目っ気すら感じられるが、そのセンスこそが彼の言うところの”空気感”を作ることであり、展示をリー・キットの作品たらしめるのだ。
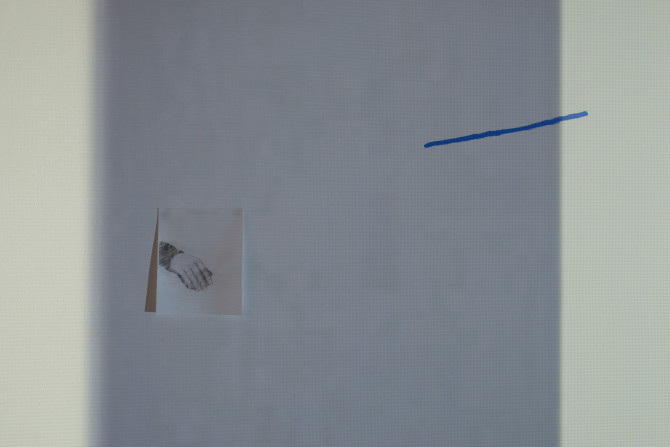
■《The Voice Behind Me》について
さて、そして今回の資生堂ギャラリーでの展示である。今回の展覧会のタイトル「The Voice Behind Me」を直訳すると、「背後から聞こえる声」。これまで何度も東京を訪れているリーが、東京という街で感じた空気感からこのタイトルをつけたという。たとえば、公園でベンチに座ったある日。天気の良い日の公園、陽の光、行き交う人々。日本の企業戦士を象徴するようなスーツを着たサラリーマンが近くに座り、携帯電話で自分には分からない言葉(日本語)で話している。
「そのとき、何か、首の後ろの辺りから声が聞こえてくるような感じがしたんだ。僕はもともと都会っ子なので、この、後頭部がざわざわっとするような感覚をいつも感じて来たし、台北やロンドンなど、他の都市でも似たような感情を感じることはある。今回の展覧会では、この感覚を共有したいと思ったんだ。」
よく知った感情でありながら、いつまでたっても慣れないよそよそしさを感じる都会特有の「不安」、「孤独」。そして「呼吸」。それが、今回の資生堂ギャラリーでの展示のテーマとなっている。

《Hands on your shoulders》(2015)は、会場奥の一番大きな空間を使い、絵画と映像によって構成された作品。映像の光が移ろうと、白を基調にした絵画の画面上に、かすかに「shiseido」のロゴが描かれているのが浮かび上がる。それは映像の光が弱まると白い画面に同化して見えなくなってしまうくらい、薄く描かれている。資生堂のロゴが入った作品ではあるが、これは今回の展覧会のために作られた作品ではなく、この展覧会が決まる前の2012年に制作されたもの。当時リーが一緒に生活していた友人のアーティストが資生堂の商品を愛用していて、その彼のために制作したものだということだが、今回奇しくも資生堂ギャラリーで展示されることとなった。そして、映像に繰り返し現れる「1」という数字と「3まで数えてみよう」という言葉は、ゆっくり「呼吸」して穏やかな気持ちを取り戻そうという、展覧会のキーワードにも通じる。
他に、スーツを着た男性が、日本にたくさんいるサラリーマンのイメージを連想させたので東京での展示に入れたという《Man in Suit》(2014)では、異なる大きさの同じイメージが配置され、さらに、立つ位置によって大きさの感覚が狂ってくる。他のすべての作品同様、近づいたり離れたりしながら、空間との関係性を重視するリーならではの空間構成を体験してほしい作品だ。


《Scratching the table surface》(2006–2011)は、リーが木製のテーブルの表面をひたすら指で引っ掻き続ける様子を映像と写真で捉えた、リーの代表作の一つだ。今回の展示では映像と写真はなく、削られたテーブルが展示されている。
テーブルの表面をひたすら削り続けるという行為は、何かをしてはいるが、そこに何も意味はないという、無意味な行為を象徴している。

「香港というなんでも効率が重視される街でこのような無意味に見える行為を行うことは、アーティストの特権だと思う。」
と言うリーは、機械的に同じ作業をしているとき、心の中はとても穏やかになれたという。そして、無意味な行為を続けることが、結果的に、効率追求型社会への静かな抵抗にもなったと語る。
「僕はトラブルメーカーだから、同じことをずっと繰り返しやっているかと思えば、何でもすぐに変えたくなったりするんだ。」
リーの作品は、香港という都市の特徴に負うところが大きいが、そのメッセージにはどこの都市にも通じる普遍性がある。一方で、リーの作品には同じアイテムが繰り返し登場するが、展示する都市によってエネルギーが違うので、異なる都市では決して同じ展示にはならないという。
また、作品の成り立ちにはパーソナルな背景を持ちながら、誰のものでもない空間として、見る人がそれぞれに自分の心の置き場所を見つけることができる。それが、世界中の人々の心を引きつける磁力となっているのだろう。

最後に、リーの現在について。
リーは2012年に香港を離れ、現在は台北に住んでいる。台北に移った理由としては、「すべてのことに効率が求められ、常に稼がなくてはいけないというプレッシャーにさらされる香港という都市で、いつしか、自分の中で大切な感情が失われてしまうと感じるようになった。その大切な感情を守るために香港からある程度の距離を取りたかった」のだという。
そして、香港を離れたことで、息苦しさはなくなったという。香港のような都市でアーティストとして無意味とも思われる行為を続けられるのはある意味特権的だけど、そのアーティストであることの意義自体変わっていくし、特権に甘んじて傲慢になりたくなかった、というリー。
そのリーが東京で見せてくれる展示では、逃れようのない不安や孤独に満ちた都会の中でも、《it really doesn’t matter》=「毎日いろんな問題が起きるけれど、大体たいしたことはないんだよ」と語りかけてくるかのようなリー自身の気配と、ポジティブで温かい感情が彷彿としてくるのを感じることができるだろう。
■最新情報
リー・キットは、香港在住のキュレーター、シャンタル・ウォンと2人で香港の九龍島にノン・プロフィットのアートスペースを立ち上げる。今年の9月にオープンする予定なので、こちらの活動も今後ウォッチしていきたい。
http://www.thingsthatcanhappen.hk



