「かっこよかった」と関西アートシーンで憧れられた作家、木下佳通代とは。「没後30年 木下佳通代」(大阪中之島美術館)担当学芸員インタビュー
「没後30年 木下佳通代」(大阪中之島美術館)会場風景
学芸員に聞く、アーティスト・木下佳通代とは
関西・神戸を拠点に1970〜90年代にかけて多くの作品を残した作家、木下佳通代(1939〜94)。国内の美術館では初となる個展「没後30年 木下佳通代」が、大阪中之島美術館で8月18日まで開催中だ。生前、関西では知られた存在であったものの、作品や作家性についてこれまで十分に検証されてきておらず、本展を機に木下の名前を知った人も多いだろう。今年10月には埼玉県立近代美術館にも巡回予定で、関東でもその作品をまとめて見られる機会となる。
木下佳通代とはどのような作家だったのか。担当学芸員の大下裕司に話を聞いた。

キャリアのスタート
──木下佳通代とはどんな作家だったのか、そして本展について、まず簡単にご説明いただけますでしょうか?
大下:木下佳通代は1970〜90年代にかけて関西は神戸や京都、大阪を中心に作品を制作しました。活動の初期には写真を用いた作品を、80年代に入ると絵画作品を発表した作家です。手法や素材が変わっても、一貫して「存在」や「認識」を抽象的な方法で表現することに取り組みました。94年に55歳で早く亡くなったこともあり、その全貌を知る機会はこれまで限られてきました。いっぽうで、関西を中心にさまざまな美術館に作品が収蔵されていて、コレクション展で見たことのある方もいらっしゃると思います。また、昨年は東京国立近代美術館で開催された小企画「女性と抽象」展でも紹介されました。目にする機会も増え、いま多くの方が「気になっている作家」のひとりなのではないかと思います。本展は、作家の没後30年という節目に、当時の時代感を含めて作品をクロニクルに紹介しています。

──木下さんの歩みはどのようなものでしょうか。
大下:木下は、1939年に現在の神戸市長田区で建具店を営む両親のもとに生まれます。ご遺族によれば、幼い頃から神戸の港で船の絵を描いていたような少女だったそうです。中学で美術部に入部、高校では部長も務めます。時代としては、ちょうど具体美術協会も活躍していた頃です。1958年に現在の京都市立芸術大学に入学して、黒田重太郎や須田国太郎からアカデミックな洋画について学びました。

木下は、植物が持つ生命力や、それらが自由に形を変えることに関心を持ったと言います。そうしたエネルギーに満ちる地球、そして宇宙へと意識は広がっていきました。在学中から、彼女が生涯に渡って追究した、「存在」とは何か、「存在」を描出するにはどういった表現が可能か、というテーマを持っていたことが伺えます。
卒業後、1963年に河口龍夫と結婚。同じく「存在」や「時間」というテーマ性が作品に色濃く出ていた河口からも少なからぬ影響を受けています。中学校の美術教師として勤めながら、河口が結成した「グループ〈位〉」の活動を手伝ったと本人は晩年に語っています。ただ、どのくらいどのように関わったのかはまだ明らかになっていません。

1970年に奥田善巳と再婚し、より理知的な油彩作品を発表する様になりました。ただ71年に発表したシリーズが情緒的に評されることを嫌い、写真作品の制作へと移行します。当時、姉弟のように「カズさん」「ケイちゃん」と呼ぶ仲だった美術家・植松奎二の協力も得ながら、「ジャパン・アート・フェスティバル」といったコンテストへの応募に加え、ギャラリー16(京都)、村松画廊(東京)などで毎年個展を開催しています。
「写真と紙」の時代
──本展の展示構成は、木下佳通代の活動の軌跡がおよそ10年ごとに分けられ、学生時代に学んだことの延長線上で制作していた油彩画をまとめた第1章、写真と紙の第2章、そして再び第3章で油彩画へと戻っていきますね。この流れのなかに彼女の制作におけるメディウムと支持体の変遷を見ることができます。
大下:よく見ていただくと、ひとつの章のなかでも、さらに細かな変化が見て取れます。たとえば「2章 1972−1981」。上述の河口や植松など、この時代には多くの作家たちが写真を用いて作品を制作していました。木下もそれに呼応するように、コンセプチュアルな写真作品を制作しました。同じイメージの連続する写真を多数並べることで、変化や差異に注目させました。たとえば時計の針の動きや、温度計の温度などを写すことで時間経過や状況の変化を示します。最初はゼラチンシルバープリントで発表していますが、次第に薄く、目の粗い質感を好み、CHペーパーという感光紙を多用するようになります。


この頃は多くの作家たちが「時間」を題材として取り扱っています。木下も、自分自身の成長変化や、街の景色の移り変わりをコラージュしてつないでみるなど、像の変化のなかに時間的なものを取り込んだ作品を手掛けています。そうした流れのなかで、短期間ですがシルクスクリーンにもトライし、多数の組写真による表現とは違う方向から、認識と空間の問題を検討していきました。

その後は「時間」というテーマから次第に離れて、木下の代表的シリーズでもある図式的な作品へと移っていきます。たとえば、コンパスで円を描いて写真に撮り、その写真の上からフェルトペンでまた円を描く。角度をつけて撮影された円は、写真のなかでは楕円に見えます。しかし、見る人はそれを、「楕円が写っている」とは思わないわけです。意識のなかではきれいな円として認識されている。イメージと認識についての問題を表現しています。

そのうち、写真としてプリントした紙そのものを、支持体ではなく作品そのものとして扱うようになっていきます。支持体とメディウムとのあいだにある、ある種の従属的な関係ではなく、被写体として写されているものと、それを写した紙との関係を、等価に扱おうとしたのです。それが突き進んだ結果、図形的なイメージから、印画紙と映された紙の実寸が重なる様な作品に帰結していきました。

再び絵画へ
──「3章 1982―1994」では、再び絵画作品へと移行しますね。
大下:カメラでイメージを作ろうと思うと、どうしても機械的な制約がついてまわる。そして、砂目のニュアンスなど望んだ表現に落とし込むために、焼き付けの作業に長い拘束時間を要します。その間は制作をストップせねばならないことに、木下は 不自由さを感じていたようです。またこの時期、第13回日本現代美術展で《作品 ’77-D》が兵庫県立近代美術館賞を受賞するなど、一定の評価も得ています。ある程度やりきったという実感もあったのでしょう。
いっぽうで若い作家の多くが写真作品に取り組み始めたこともあり、写真の制作から離れていきます。より制約なく、身体的に制作ができるということで、フェルトペンからパステルへ、パステルから油彩へと変化していきます。


80年代初頭は、作風の模索の時期でした。アトリエの火災で作品を焼失するなどして、本人曰く「しんどかった時期」に、これまでの理知的な思考に基づく作風から離れ、画面いっぱいに塗り込み、その上から布で拭うという、より身体的で直接的な抽象表現に変わっていきます。よく見ると、画面の縁(ふち)には色が塗られていない箇所があります。木下は、画面をすべて塗りきらないことで、色面と同時に、キャンバスの存在をあえて認識させようとしたのです。そうしてしばらくは「描く」と「消す」を繰り返しながら、色面の存在をとらえようとしていました。やがてそれは筆致としての「線」に変わっていき、だんだんその線の本数も、画面から減っていきました。


その後も新たな展開を構想していた木下ですが、晩年はがんに冒され、思うように制作に向かえない日々が続きます。手術を拒んだ木下は民間療法を求めてロサンゼルスに滞在しました。帰国後、亡くなる前年の93年に発表したのは、これまでのコンセプトを集結したような作品でした。色面と奥行きの問題、様々な筆致、塗って消すという行為をひとつの画面に集約させていて、非常に見応えがあります。


「かっこいい」と評される作家像
──木下さんの抽象絵画は、たとえばこのブラッシュストロークは一見勢いで描いているようにも見えますが、実際はそうではないですよね。ひとつひとつを丁寧に面として塗っているというか。
大下:そこが非常に作家性の表れている部分だと思います。木下は制作プロセスとして、まずは頭のなかでしっかりと設計してから、手を動かしていたと私は考えています。本人が明言しているわけではないのですが、初期の制作手法を考えると、線の濃淡、太さ、92年以降の作品にみられる絵具の「垂れ」なども、綿密に考えられていたのではないかと。

それが如実に表れているのが写真作品で、特に折った紙を写したシリーズでは、紙の折る角度や折りこむ幅を計算して、事前に設計しています。ドローイングもたくさん残されているのですが、その殆どにサインとタイトルが付されていて、本人のなかでは習作ではなく、それぞれがひとつの作品だったようです。
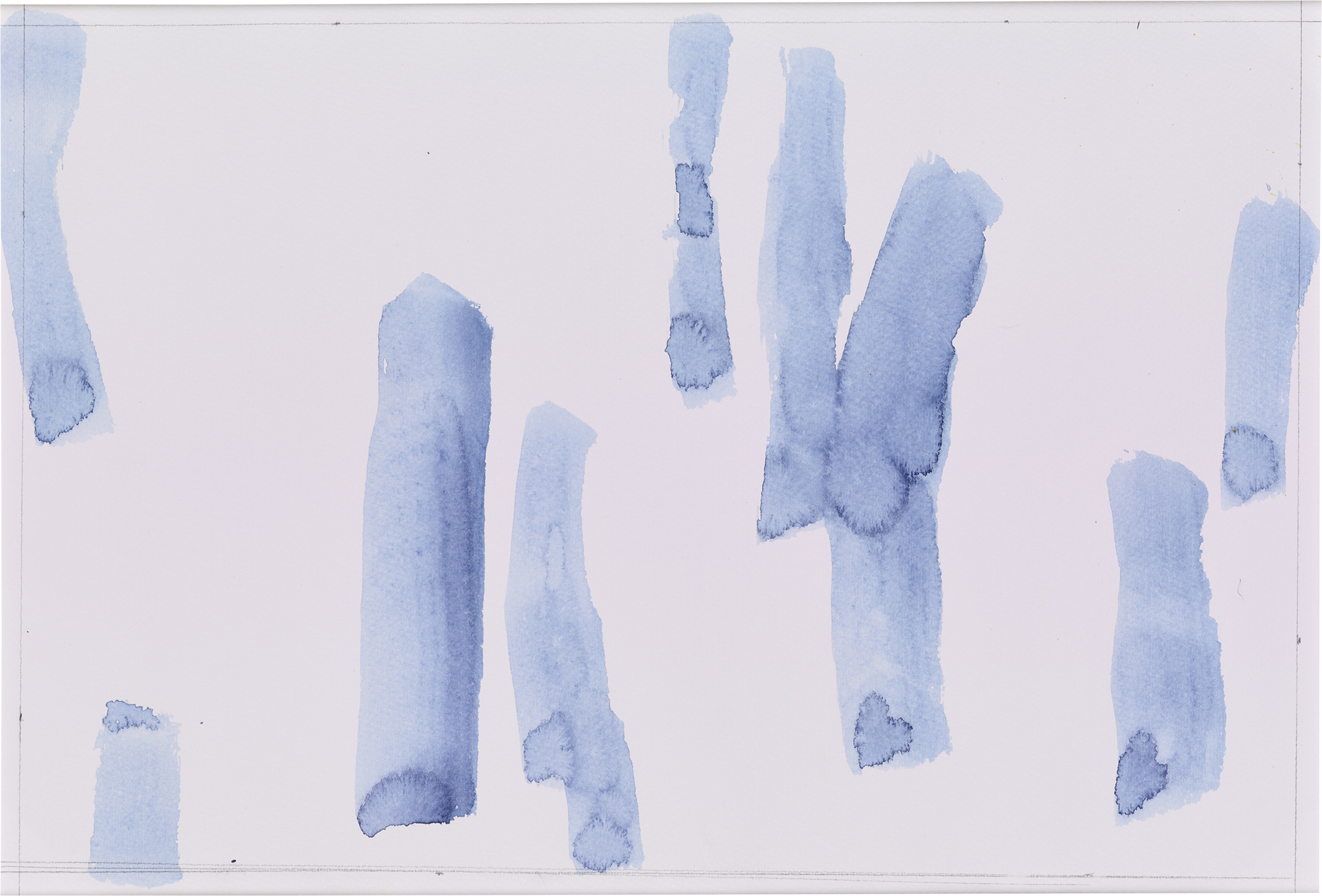
──そのときどきの情動に突き動かされるのではなく、非常に理知的に制作をされていらした方なんですね。
大下:生前お会いになっていた方々に話を聞くと、皆さん口を揃えて木下のことを「かっこよかった」と話しています。本当にスマートで、憧れる作家だったと。キリッとして歯に衣着せぬ物言いで、ズバッとなんでも言ってしまう強さもあったそうです。反面、感情豊かな方でもあったのでしょう。人と交流することがとても好きで、1階が絵画教室、2階が生活空間というスペースを設けて、そこに植松奎二さんはもちろん、辰野登恵子さんら関東でもよく知られた作家仲間がいつものように集まっていたようです。また根っからの子供好きだったそうで、子供たちにも絵を教えていました。喫茶店をやっていた時期もありました。

いま「木下佳通代展」をやる理由
──そんな木下佳通代の展覧会を、没後30年の節目とはいえ、なぜいま、このタイミングで開催することになったのでしょうか?
大下:私が木下佳通代という作家をきちんと認識したのは、2018年に当館の準備室に着任してからでした。私自身ほとんど知らなかったこの作家の作品が、当館では当時20点以上収蔵されていました。また関西の多くの美術館で少なからず収蔵されているということも知り、この作家に対する関西と関東での認知の差に驚きました。また、ヒューストン美術館で開催された『来るべき世界の為に 1968年から1979年における日本美術・写真における実験』展(2015)への出品をはじめ、バーゼル香港などで紹介された状況から、国際的な注目を集めつつある作家であることも分かった。日本国内でも、女性作家の再評価が進んでいる現在、木下の活動をぜひとも取り上げたいと思いました。
それからなにより、当時の木下を知る関係者の多くがご健在で、作家や当時の状況について、聞き取りがたくさんできたことも恵まれていました。木下自身、存命であれば85歳。それゆえ調査にご協力頂いた方にはご高齢の方も多く、こうしてお話を伺えたのは幸運だったことに間違いありません。
今年10月から、本展は埼玉県立近代美術館に巡回します。展示する作品こそ同じでも、関西と関東では目指すところが少し異なります。関西では個展として紹介することで作家の全体像を知る機会となることを期待するのに対し、そもそも展示機会の少なかった関東ではある種のデビュー戦というか、「認識してもらうための展覧会」となるのではないでしょうか。

──海外のマーケットではどのような文脈で評価されるのでしょう?
大下:海外のマーケットが、「具体」や「もの派」に続く日本の戦後美術作品を探しているという状況があると思います。そのなかで、木下はまだあまり知られていません。本人は亡くなる直前、写真作品は評価されたが、ペインティングがまだ評価されていないと悔やんでいたそうです。本展では、作家の生涯を通して作品をお見せすることで、晩年まで「存在」というテーマを一貫して取り上げた木下佳通代の作家性を、きちんとご紹介することができたのではないかと思っています。

関西の美術館関係者たちのエールを受けて実現
──そもそも、木下さんの作品が関西の多くの美術館で所蔵されているのはどういった理由があるのでしょう?
大下:木下と同時代の美術館の学芸員や美術批評家が注目していた作家だったというのが当然あります。たとえば、西宮市大谷記念美術館の館長だった故・越智裕二郎さんや、京都市美術館の平野重光さんや中谷至宏さん、兵庫県立近代美術館(当時)の中島徳博さんなどが、熱心に研究されていました。当館準備室におり、後に和歌山県立近代美術館の館長を勤めた熊田司さんもそのひとりです。評価した批評家の中には中原佑介や高橋亨、乾由明などがいます。
また、大阪にあったAD&Aが晩年、木下佳通代の展覧会を開催しており、唯一のモノグラフを刊行しています。AD&Aは木下の没後、各地の美術館に作品が収まるよう尽くされたそうです。今回の展覧会でお借りした作品の多くが、所蔵履歴にAD&Aの名前を載せています。

──関西の主要な美術館に収蔵されながら、これまであまりまとめて紹介される機会がなかったというのはなぜでしょう。
大下:木下が55歳と早く亡くなっているということが大きいと思います。加えて90年代に入って、ニュー・ペインティングや関西ニューウェーブなどの新しい美術動向に注目が集まったこと、当時まだ男性作家の個展の方が先行して開催されていたなど様々な理由が想像できます。
世界的に美術史における女性作家の再評価という動きはありますが、私としては木下が女性作家だから評価できるというよりも、その作品・活動などから当然取り上げるべき重要な作家だろうとの認識で企画しています。また、美術に関する言説の発信地が昔もいまも東京中心となっているとすると、関西を拠点にした作家がこぼれてきたという側面もあるでしょう。
ちなみに本展では、木下作品を所蔵するほぼすべての館から作品をお借りすることができました。皆様こころよく作品をお貸出しくださり、「こういう機会を作ってくれてありがたい」と言っていただくことも多く、背中を押していただいたように思います。本展を機に、さらに研究・検証が進むと嬉しいです。まだわからないことも多く残っています。
今回の展覧会に際して刊行したカタログもぜひ見ていただきたいです。熊田司さん、光田ゆりさん、埼玉県立近代美術館の建畠晢館長にご寄稿いただきました。また作家と交友の深かった植松奎二さんのインタビューを掲載するなど、300ページを超える大著になりました。ぜひ、お手に取ってみてください。
──とても有意義で見応えのある展覧会ですし、これを機に木下さんのことを多くの人に知ってほしいですね。どうもありがとうございました。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)
「Tokyo Art Beat」編集長



