トークイベント『アートの未来:作品体験とアーキテクチャ』
2009年12月23日にCAMP主催で、トークイベント『アートの未来:作品体験とアーキテクチャ』が開催されました。CAMPは、同時代の表現や文化(政治や経済なども含む)を考えることを目的とした企画を行う団体で、これまでもさまざまなスペースでトークイベントを開催している団体です。
『アートの未来:作品体験とアーキテクチャ』と題した今回は、4人をゲストに迎え「アーキテクチャ」をキーワードに行われました。アーキテクチャとは建築様式や構造を指す言葉ですが、最近は社会の仕組みやウェブのシステム構造など、広義の意味での「構造=アーキテクチャ」という使われ方をしています。ここでいう「アーキテクチャ」とは「ものごとの仕組み」といった広い意味を指します。

全体は3部構成になっていて、第1部は辻憲行さん(東京都写真美術館学芸員)、星野太さん(東京大学大学院総合文化研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員/TABlogゲストライター)、濱野智史さん(情報環境研究者/『アーキテクチャの生態系』著者)による「雑談」。第2部からは光岡寿郎さん(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員)が加わり、各スピーカーの「プレゼンタイム」。第3部は1・2部の内容を受けての「ディスカッション」が行われました。
「雑談」もディスカッションもともに興味深い内容でしたが、今回はゲスト陣によるプレゼンテーションをレポートしたいと思います。
まず、ここでアーキテクチャという言葉を軸に「アートの未来」「作品体験」を考える各々の視点を確認しましょう。
■ 辻さんは、学芸員という立場から、美術館で作品を展示するというアーキテクチャ(仕組み)に疑問を抱き、ウェブやCATVといったメディアを通すことで個人的空間で作品体験を成り立たせた過去事例を出しながら、作品体験の変化を紹介。
■ メディア研究者の光岡さんはメディアとしての美術館に、コミュニケーションツール(カメラ付き携帯電話など)が入り込んだことに着目し、作品体験の質の変化・メディアの変化を指摘。
■ 美学、表象文化論を専門とする星野さんは、作品を体験する側の私たちそのものに注目し、”直接体験”が虚構だということを踏まえた上で、これから来るアート作品の手法を示唆。
■ 情報環境研究者の濱野さんは19~20世紀の複製技術が手放してしまったアウラ(*1)が21世紀にウェブのアーキテクチャによってライト・アウラとして生成されている現実を踏まえた上で、アーティストの役割を問う。
それでは、4人の「アーキテクチャ」へのアプローチをもう少し詳しく見ていきましょう!
■<体験する場・仕組み>映像作品の享受のアーキテクチャの変化
辻さんは、自身が企画し秋吉台国際芸術村のレジデンス事業の中で開催した、参加アーティスト(14組、18人)による展覧会『CHANNEL_0』の紹介をしました。この展覧会は、インターネットによる動画配信が普及し始めた2004年の11月1日~12月6日に行われました。山口県の山口市、防府市、宇部市を中心とした地域で、約20万世帯で放映されるCATVやインターネットを通したビデオ・ストリーミング配信による映像作品の展覧会でした。「美術館」という特定の場所を持たない展示方法が特徴です。
当時は、インターネットのインフラ整備や誰が見ているのか、盛り上がっているのかわからない<いま・ここ>問題があったが、現在はその問題も乗り越えているので(特に人を集めづらい土地では)美術館で展示するという仕組み(アーキテクチャ)を再検討できるのではないかとの見解を述べました。
■<体験するメディアの変化>作品体験の質や体験の仕方そのものの変化を指摘。
光岡さんは、携帯電話やコンパクトカメラなどで作品を撮影している人々が、海外を中心に急増していることを紹介しました。彼らは美術館の中で作品鑑賞よりも撮影に集中し、その画像に「かわいい」や「青い」などといった単純なタグ(分類用の情報)を付けて、Flickrなどの写真共有サービスやブログにアップしていきます。
一眼レフカメラを持っているのに携帯カメラで撮影している事例を紹介した上で、撮影の目的はアーカイブ(一眼レフカメラ)ではなく、コミュニケーション(携帯カメラ)ではないかとの指摘をしました。
そもそも「盗み見る」という言葉が示すように、見るという行為には所有するという含意が強く反映しており、美術館という装置が鑑賞という形式で所有を代行していた側面もあるのではないか、だから美術館で一番売れているものは(所有欲を満たす)絵葉書。そして今はウェブ上の画像で見るという所有が行われている。
そのことを踏まえると、ウェブに無数の作品画像が存在する現在、美術館の仕組み(アーキテクチャ)は長い歴史におけるメディアの一形式の可能性があるとの見解を示しました。
■<インターフェイスの再考>直接的な作品体験はそもそも存在しない。
星野さんは<作品を体験するとはどういうことなのか>と、鑑賞者に焦点を当てた根源的な問題提起をし<直接経験は存在しない>と結論づけました。
ここで挙げた命題は<作品を「直接的に=メディアの媒介なしに」経験することは可能か>ということで、メディアとは網膜やニューロンなどの感覚・伝達器官を指しています。その意味においては何らかのメディアの媒介なしには、作品体験はありえないので直接体験はありえません。様々な器官を通して体験するということは、複数のインターフェイスがあるということで、ダイレクトな(一つの)感覚は存在せず、複数の異なった情報が、異なったまま脳の中に入ってきて一つの体験として再構成されているに過ぎない。そしてそれまでに経験した映像や音の記憶と、新しく経験した作品の知覚がぶつかり合う。それはつまりマッシュアップまたはMAD的な認知とも言える。現物の絵画体験は複製品より「直接性が高い」と言われるが、実際にあるのは現物の絵画の持つ情報量の違いだけ。
また菊地成孔・大谷能生著『アフロ・ディズニー』によると、映画がしたことは、視覚と聴覚を一度分断した後、再接合(編集)したものを作品として体験させた。それに対して21世紀のアートはMAD的なものとなるだろうとの見解を示しました。
■<アート、アーティストの再定義>いま・ここ。ライト・アウラが生成される
濱野さんは、門林岳史の著書『ホワッチャドゥーイン、マーシャル・マクルーハン?』からハーバート・マーシャル・マクルーハン(「メディアはメッセージである」というテレビメディア論を展開した、アノ人です!)の言葉を引用しながら、「「アートの未来」ではなく、<未来の早期警報システム」こそがアート>との見解を示しました。
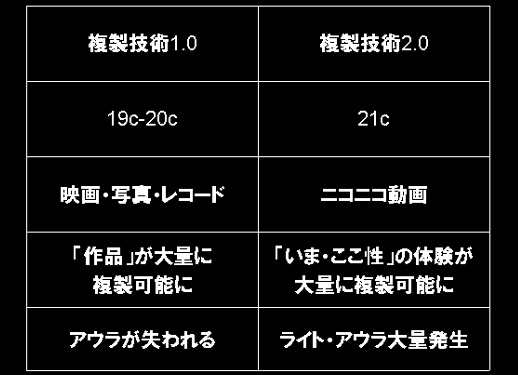
その上で、2009年に開催された東京国立近代美術館『ヴィデオを待ちながら 映像、60年代から今日へ』、第一部「鏡と反映」について言及。
アンディ・ウォーホルの『アウター・アンド・インナー・スペース』、リチャード・セラ+ナンシー・ホルト『ブーメラン』の作品を引用し、自分の声が数カウント後に跳ね返り続けることで自己の存在そのものが問われるこの作品群は「再帰的近代」(鏡に映る自分を見つめるように、自己を常に反省的にモニタリングせねばならないという、近代社会の特徴を捉えた概念)における自己同一性の脱構築と読み取れる映像作品。
19~21世紀は複製技術によってオリジナルがもつ<一奇跡/一回性>といったアウラが失われてしまったことも指摘。 しかし、ニコニコ動画では擬似同期が可能で「ポリクロニック・アーキテクチャ」(多時間的環境)を持ち一回性だったアウラが簡単に生成(ライト・アウラ)される。そして重要なのは、そのズレにより本来引き起こされるはずの「反省」が「w(「笑う」という意味を持つ絵文字)」になっていると説明。その上で「こうしたアーキテクチャが出てきてしまったとき、「芸術家」の役割とは何か?」という問題提起をし、プレゼンを締めくくりました。
以上のプレゼンは、元来考えられてきた作品体験の手法や身体、場所・アートの意義からの開放・解体の試みが始まっていることを伝えているようにも読み取れました。
そして、ゲストにアーティストが含まれていなかったというのは、「アーティストはこれを踏まえて、未来を考えて!」という問いかけではないでしょうか。
ですので、私はこれを受けてこれからのアーティストやアートのことを考えてみました。
■アーティストの可能性なのか、アートの可能性なのか
それでは、ここからの後半では、濱野さんの問題提起<こうしたアーキテクチャが出てきてしまったとき、「芸術家」の役割とは何か?>という問いについて、お話を進めていきますね。
社会的には「共通意識・共通言語があるオタクだけが楽しめる動画サイト」という位置づけのニコニコ動画を「社会学的に意味のあるもの」として著書の中で教えてくれたのが濱野さんです。著書を読んだ多くの方はニコニコ動画に対する見方が変わったのではないでしょうか。彼はニコニコ動画を開発した人物ではありませんが、著書やレクチャーやシンポジウムを通して、ニコニコ動画の特殊なアーキテクチャを社会に提示してくれました。
それになぞらえるなら、『「社会学的に意味のあるアーキテクチャ」を持ったニコニコ動画を、アートの現場でアーティストがどう捕らえるか』という問題設定ではなく、『「芸術作品としてのアーキテクチャ」を持ちえるニコニコ動画の可能性をアートの現場でどう取り上げていくべきか』という問題設定でアートの未来を考えてみた方が自然ではないでしょうか。
それは、アーティストがニコニコ動画に対抗・抵抗・類似した作品の可能性を考えるより、ニコニコ動画というアーティスト不在の「アーキテクチャ」が作品となりえるような批評群を展開していく未来のほうが、今回のタイトル『アートの未来:作品体験とアーキテクチャ』らしいなと思ったこと、
そして、手法ではなくアーキテクチャ(仕組み)を作品と考える方がジャンルに回収されにくくなり、広い作品展開ができるので作品の質が見やすくなるのではと考えるからです。
作品をジャンル分けしてしまうと、今まで繰り返してきたように「あのジャンルは、気休めだ。」といったような発言がしやすくなります。それは各ジャンルの中にも質の違いがあることを目隠しする言葉にも簡単になりえます。
光岡さんがプレゼンしたように、(作品をジャンル分けではなく)タグづけしていき、様々なタグから作品にアクセスできるようになれば、アートの現場や鑑賞の現場はもっと面白く、活気がつきそうです。
■ここからはユミソンさん(私です)の妄想提言です
たとえば身体のないアーティストを人格化し、ニコニコ動画のアーキテクチャを作品として世界に提示するという方法もあります。(個々の動画を芸術作品と言ってないですよ。念のため!)法人という法の力で権利能力を持った「人」が既に存在していますし、会社や団体という実体のないモノ、例えばナイキや資生堂などの企業ブランドに私たちが人格的イメージを抱くことに抵抗のない今の世界では、それはさして難しくも目新しいことでもないと思います。
この場合の「人」とは<真理>を持った、たった一人という意味ではなく、数多くの固有の身体を持たない人を指すのであって、こういった「人」がアーティストとして量産されるということが想定されることでしょう。
以上に倣って見ると、広島市現代美術館にて2010年2月21日(日)まで開催されている『一人快芸術』展は今、注目すべき展覧会と言えます。参加作家一覧を見たところ、アートの世界で「アーティスト」として活動している方よりも、鶴見俊輔の唱える<非専門的芸術家によって作られ大衆によって享受される芸術>、限界芸術(*2)を実践しているような人々が多く参加しているようです。
美術館がこのような展覧会を開催する現実は(限界芸術というジャンルを紹介している展覧会と読むより)、連続する身体のないアーティストが作る作品の可能性の未来を暗示しているようです。このような流れをロウ・アートと呼ばれるものだけにせず、ハイ・アートでも展開していったり、世界に紹介していったりする作業に期待したいです。
そもそもアーティストの身体とアーティストの寿命というは、ズレのあるものです。そしてアーティストの自我や存在の消去なんてことは、連綿と続けられてきているので、もっと推し進める形で展開できますし、現在の資本主義らしい当然の流れとも言えます(今更ぽいけど)。
なーんてことをCAMPでの4名によるプレゼンのコールに対してのレスポンスとしたいです。
とはいえ、私は身体がある上で作品を作っているので、もし身体を持たないアーティストの存在が批評の場を超えて存続し続け、世界を魅了したならば、「むかつくー!うがぁ。」とか遠くで叫ぶかもしれません(笑)。私は対峙した立場にありながら、アーティストとして様々なアーティストの可能性の望みます。それは抵抗勢力や複数の思想や思考が常に乱立しているサマが好きだからです。
(*1) ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』参照
(*2) 福住廉の著書『今日の限界芸術』参照
yumisong
yumisong



