本から広がるアートの世界:美術批評家が選ぶ、新刊をチェックしたい出版社10社
注目の作品集、写真集、気鋭の批評家による論考など、毎月出版される注目の美術書。それらのラインナップを知るには、書店の一角や雑誌のカルチャーページ、SNSなどさまざまな入り口があるが「出版社」から本を選んでみるのもひとつの手。
美術批評家の中島水緒が、重要な美術書を世に出してきた日本の出版社10社を紹介。外出が難しい日々には、本から美術を知る経験も楽しんでほしい。

硬軟ともに幅広いラインナップ「フィルムアート社」
1968年、雑誌『季刊フィルム』の創刊をきっかけに設立。映画・映像関連の書籍を中心に、美術、演劇、写真から文学まで幅広いラインナップを誇る。作り手や書き手を育てるための創作術、観賞や批評の手引きとなるリテラシー入門など、表現に関わる人たちを応援する企画を数多く手掛けている。アートの見方や編集論、キュレーターの仕事を紹介した「Next Creatorシリーズ」もそのひとつだ。また、参加型アートの歴史的検証として必須文献のクレア・ビショップ『人工地獄』(2016)、現場で活躍する専門家の言葉を集めた『アートプロジェクトの悩み』(2016)、芸術家たちの日々の習慣をエッセイ形式で紹介する『天才たちの日課』(2014)、意外な切り口で話題を呼んだ原田裕規編著『ラッセンとは何だったのか?』(2013)など、読み応えのある良書を硬軟ともに揃えている。ウェブサイトが充実しており試し読みのページもあるので、ジャンルを超えて関心を広げたい人はマメにチェックするとよいだろう。ウェブマガジン「かみのたね」には多彩な執筆陣が寄稿。
http://filmart.co.jp

若手研究者の単著にも積極的な「水声社」
1981年、「書肆風の薔薇」として創業し、91年に現在の社名に改称。文学、芸術、現代思想など人文系をメインに出版する。「風の薔薇」時代で言えば、宮川淳、小林康夫といったフランス現代思想系をバックボーンとする論者たちの本が印象的だったが、フランス系に限らない守備範囲の広さも魅力のひとつで、美術書のラインナップもかなり多彩である。美術家・白川昌生の一連の著作、マニアックなシュリレアリストも取り上げた「シュルレアリスムの25時」シリーズを刊行するほか、若手研究者の優れた仕事の書籍化にも積極的だ。伊藤亜紗『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(2013)、荒川徹『ドナルド・ジャッド』(2019)など、注目の書き手が水声社から初の単著を出したケースも少なくない。シュルレアリスム、ジャン=リュック・ナンシーなどを特集してきた定期刊行物『水声通信』も毎号充実の論考を掲載しているのでチェックしておきたい。Amazonに出荷しないポリシーを貫いているが、自社のブログやTwitterで最新の刊行情報を確認できる。
http://www.suiseisha.net/

100年以上におよぶ歴史「美術出版社」
言わずと知れた美術系出版社の老舗。創業は1905年。出版社の「顔」ともいうべき雑誌『美術手帖』は2018年から隔月刊行に移行した。他方、時事的な話題にも対応できるメディアとして2017年に始動したのがWEB版「美術手帖」だ。同サイトでは、ニュース、レビュー、インタビューなどを毎日発信。近年は豊富なコンテンツを揃えるWEB版が精力的に活動している印象だが、一世紀以上に及ぶ歴史の中で生み出した美術書の数々も基本として目を通しておきたい。『西洋美術史』『日本美術史』など版を重ねて読まれてきた定番の概説書、「美術検定」の関連書籍、展覧会カタログなどを制作するほか、『美術手帖』での連載をまとめた椹木野衣『後美術論』(2015)、『震美術論』(2017)、大森俊克『コンテンポラリー・ファインアート』(2014)など、気鋭の論者による評論集も刊行している。『美術手帖』誌の特集が書籍化されることもあるので、気になる内容のものは保存版として手元に置いておきたい。
https://www.bijutsu.press/
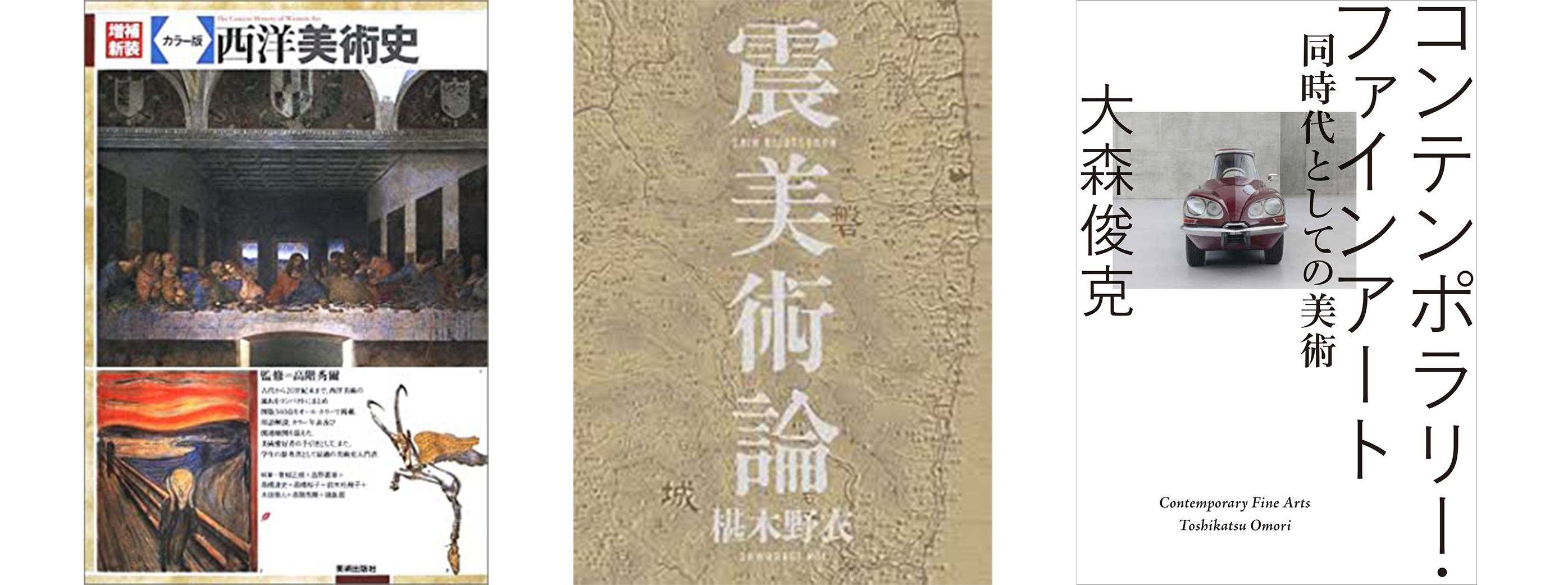
Instagramやnoteも活用「青幻舎」
出版界には「青」が社名につく出版社がなぜか多く存在する。「当代の芸術の存在感を顕す」をモットーとし、京都と東京を拠点に活動する青幻舎もそのひとつ。現代美術、写真、デザインから建築まで、ビジュアルブックを主に専門とする出版社である。会田誠、山口晃、小林孝亘ら、日本の現代美術界を代表する作家たちの展覧会カタログや作品集に加え、畠山直哉、松江泰治、川内倫子、金川晋吾らの写真集を刊行するなど、同時代のアート全般をバックアップしている。絵画史に関心を持つ読者であれば、デイヴィッド・ホックニーの刺激的な絵画論が展開される『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』(2017)は必読だろう。また、展覧会の記録集で言えば、『ドキュメント 14の夕べ』(2013)のような挑戦的な体裁に挑んだ書籍も忘れ難い。自社のInstagramとnoteを運用するほか、ブックフェアへの出展も多いので、さまざまなメディア・場所で青幻舎の本に出会えるはずだ。
http://www.seigensha.com/
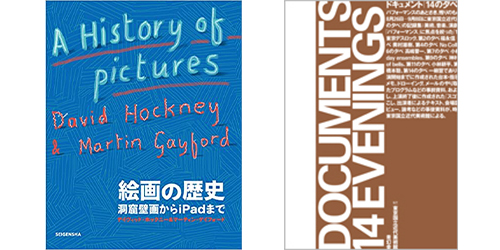
美術を本格的に学ぶ人は必ず通る「中央公論美術出版」
1956年、中央公論社の幹部だった栗本和夫が創業。堅実な歩みの中で、美術史・建築史の学術的な専門書を数多く刊行している。当初は『池大雅画譜』『浦上玉堂画譜』をはじめとする日本画家の作品集を数多く手掛けていた。図版が充実した大判の画集や研究論集を厳粛に函から取り出し、作品や言説にじっくり触れる体験は何物にも代え難いものだ。また、調べ物の際に『日本美術年鑑』といった資料類にお世話になった人もきっと多いのではないか。研究者、専門家、図書館向けの本が中心なので、一般人には手の届きにくい高価な本も多いが、昨年刊行を開始した「新装版 バウハウス叢書」(全14巻)のように比較的廉価のシリーズがあるのも有難い。美術を本格的に学びたい人は必ず通過する出版社と言えるだろう。
http://www.chukobi.co.jp/

知的興奮に満ちた読書体験「三元社」
国内外の書き手問わず、高い水準の人文書・美術書を刊行する。美学・美術史、芸術史に関連するアカデミックな研究書や理論書を幅広く揃えており、深く学びたい人に濃密で知的興奮に満ちた読書体験を約束してくれる。アーサー・C・ダントーの待望の邦訳『芸術の終焉のあと』(2016)、卓越したラウシェンバーグ論である池上裕子『越境と覇権』(2015)、17世紀スペイン絵画を分析するヴィクトル・I・ストイキツァ『幻視絵画の詩学』(2009)、ユニークな論点が興味深い松下哲也『ヘンリー・フューズリの画法』(2018)。この一覧からも古典から現代までを網羅するヴァリエーションの豊かさがわかるだろう。定期刊行物『西洋美術研究』も刊行しており、これまで「美術市場と画商」「イコノクラスム」「パレルゴン」などのテーマで特集を組んでいる。
http://www.sangensha.co.jp/

個性を打ち出すひとり出版社「アートダイバー」
2014年創業の若い出版社。元美術雑誌編集者の細川英一が代表を務め、大手や中堅とは異なる「ひとり出版社」ならではの個性的な路線を打ち出す。梅津庸一『ラムからマトン』(2015)、中村ケンゴ編著『20世紀末・日本の美術』(2015)といった批評性の強い書籍から、鳥取の前衛芸術家集団「スペース・プラン」を再評価する記録集までを刊行。また、中ザワヒデキ『現代美術史日本篇 1945-2014』(2014)、荒木慎也『石膏デッサンの100年』(2018)のように少部数で過去に完売してしまった書籍を再版するなど、読まれるべき本を世に送り出す仕事からもポリシーが伺える。2018年には画家・小林正人による自伝小説3部作の1作目を刊行し、新たな領域を開拓した。
https://artdiver.tokyo/
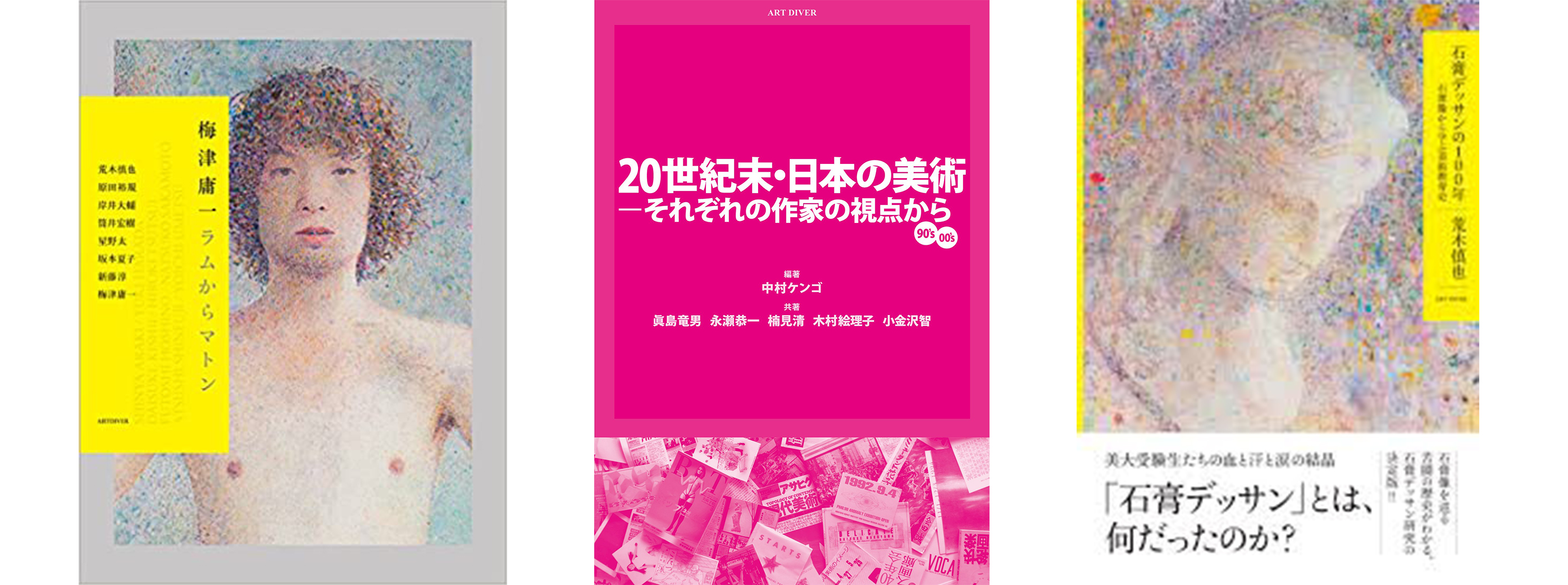
木村伊兵衛写真賞の受賞作も多数「赤々舎」
2006年設立。主に写真と現代美術の作品集を扱う。青幻舎を経て独立した姫野希美が代表を務め、現在は京都を拠点に活動する。ほとんど無名に近い新人からベテランまで、写真表現の可能性を感じさせる作品であればキャリアを問わずにサポート。志賀理江子『CANARY』(2007)、浅田政志『浅田家』(2008)、百々新『対岸』(2012)など、木村伊兵衛写真賞の受賞作を数多く手掛けていることでも注目を集めている。そのほか、世界最初の写真集であるトルボット『自然の鉛筆』の日本語版(2016)、畠山直哉と大竹昭子の対談を集めた『出来事と写真』(2016)、竹内万里子の批評集『沈黙とイメージ』(2018)など、話題の書籍を継続的に刊行する。作家と並走しながら書籍をつくりあげていく出版社だ。
http://www.akaaka.com/

マニアックなアプローチ「森話社」
人文系の書籍を扱う出版社。日本文学、歴史、民俗学、芸能・演劇、映像・映画関連を中心とするが、芸術系の良書も発信している。西村智弘、金子遊編『アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ』(2016)は、マヤ・デレン、アンディ・ウォーホル、ロバート・スミッソンらの実験的な映像作品を扱った通好みの論考集。西村智弘『日本のアニメーションはいかにして成立したのか』(2018)は、日本の実験アニメーションの歴史に光を当てた貴重な研究な成果だ。スポーツとアートの交差する領域に着目した中尾拓哉編『スポーツ/アート』(2020)、1950年代の大衆文化やメディア状況を考察する鳥羽耕史・山本直樹編『転形期のメディオロジー』(2019)等々、興味深い切り口の書籍は他にもたくさんある。マニアックなアプローチも含めて今後の展開に注目したい。
http://www.shinwasha.com/

美しい装幀にも注目「月曜社」
2000年設立。現代思想、哲学、カルチュラル・スタディーズ系の書籍を主に刊行。人文系の知を担う存在として定評を得る一方で、美術書や芸術理論、展覧会カタログ、森山大道の写真集などを出版している。星野太『崇高の修辞学』(2017)、筧菜奈子『ジャクソン・ポロック』(2019)といった優れた若手の仕事を紹介するほか、近年ではロザリンド・E・クラウス『視覚的無意識』(2019)の待望の邦訳が話題を呼んだ。現代思想や芸術哲学へと関心を羽ばたかせたい人は、ジョルジョ・アガンベン、ジャン=リュック・ナンシーといった知の巨人たちの著作に学ぶこともできる。2018年からは〈哲学への扉〉シリーズを刊行。美しい装幀が多いのも月曜社の本の魅力のひとつ。ちなみに代表の小林浩が運用するブログ「ウラゲツブログ」では他社の新刊情報も積極的に発信しているので、読書狂ならずともチェックしておきたい。
http://getsuyosha.jp/

–
中島水緒
1979年、東京都生まれ。美術批評。和光大学人文学部芸術学科卒。主なテキストに、「「恋愛映画」は誰のためにあるのか――「(500)日のサマー」における「真実」と「言葉」」(私家版、2014年)、「鏡の国のモランディ――1950年代以降の作品を「反転」の操作から読む」(『引込線 2017』、引込線実行委員会、2017年)など。自身のWebサイトにて、論考「沈黙の形態――1940年代のジョルジョ・モランディ」(2015-16年)、「イタリア近現代美術年表」を公開。



