東日本大震災の後、自分は変わったと思いますか?:畠山直哉に5つの質問
2021年3月11日、東日本大震災の発生から10年を迎える。震災を起点としたこの10年間に、人々は何を考えどのように行動してきたのか? アーティストや関係者にインタビューを行い、忘れ得ない出来事、人間が学ぶ教訓としての震災を振り返るとともに、今後を展望する。
第2回は岩手県陸前高田市出身の写真家、畠山直哉のオンラインインタビュー。自然、都市、写真の関わり合いにフォーカスした作品で知られる畠山は、2011年10月、東京都現代美術館での個展「ナチュラル・ストーリーズ」で震災前・後の陸前高田の風景作品を初めて発表し、その後も写真集「気仙川」、「陸前高田 2011-2014」(2015年)、せんだいメディアテークでの個展「まっぷたつの風景」(2016~17年)と故郷と関わる制作活動を行ってきた。(インタビュー・構成:永田晶子[美術ジャーナリスト])
1:東日本大震災が起きた瞬間、畠山さんは何をしていましたか?
東京・赤坂にある写真のラボにいました。「フォトグラファーズ・ラボラトリー」と言い、いまどき珍しいネガからプリントを引き伸ばせるラボです。立ち会い作業でプリントをつくっていました。ものすごく揺れ、マンションの半地下にあるラボから急いで外へ出ました。外壁にひびが入る音、子どもが泣き叫ぶ声が聞こえましたね。見上げると、壁の破片やほこりがたくさん落ちてきました。揺れが収まったのでラボに戻るとテレビがついていて、ただごとではないと報道からわかりました。震源地は東北宮城県沖だとわかりましたが、その時はあれほど大変な災害になると思いませんでした。あちらと全然連絡がつかず心配でたまりませんでしたが、現像液は駄目にならなかったので、ラボの人に「作業を続けませんか」と言われ、何をすべきかわからなかったのでプリントを続行しました。

──どの作品のプリントをしていたのですか。
「BLAST」の大きなプリントです。夕方まで作業を続け、帰ろうとしたら交通機関がまったく動いていなくて、道路の混雑もひどかった。家人に電話してオートバイで迎えに来てもらい、二人乗りして自宅に帰りました。津波のニュースは聞いていましたが、陸前高田がどうなったか、そこにいる母や姉が無事かどうか、一切わかりませんでした。電話しても通じないし、誰に聞いても知らない。時間が流れるのに身を任せる感じでした。陸前高田のニュース映像は流れていましたが、実家がある気仙町の様子はわかりませんでした。
希望的観測ってありますよね。つまり「大丈夫だ」「きっと無事だ」と、心のどこかで思ってしまう。ある哲学者が「墜落している飛行機の中でも自分だけは助かるかもしれないと思うだろう」という趣旨を述べていますが、そう思うように人間はできているんじゃないですかね。根拠がない信じ込みを抱いて1、2日過ごしました。仕事にも行きました。もう自分で行くしかないと思い、バイクで出発したのが14日。その頃、陸前高田の丘の上にある泉増寺から新聞記者が撮影した写真がネットにアップされ、見ると気仙町は水面下になっていて大木の先が少し見えているだけでした。これはだめだと思った。SNSにはさまざまな情報は流れていましたが、僕には役に立ちませんでした。誤った情報も流れていました。バイクで新潟県の北部を走っている最中に親戚からみんな無事だとネットに出ていると、携帯に連絡が入りましたが、それも誤りでした。5日かけて陸前高田にたどり着き、19日に母の遺体を確認しました。
出かける時にいつものようにカメラと小型の三脚をバイクに積みました。当時使っていたフィルムは手持ちで撮るのは難しいので、常に三脚を使っていました。普段の三脚は少し大きいので、平たく畳める小型のものを買いました。

──畠山さんは陸前高田市で生まれ、大学に入るまで育ちました。震災前と震災後、そして10年がたち、地域はどう変化しましたか。
宮城なら登米、岩手なら花泉といった津波被害に合わなかった内陸の町に行くと、懐かしい気持ちになります。昭和の記憶が残る雰囲気がかつての陸前高田に似ているからです。宮城の本吉(気仙沼市)は沿岸部ですが、津波が来なかった場所があり、そこを通ると実家があった気仙町はこんな雰囲気だったと思うこともあります。時代が積み重なった陸前高田の町が消えてしまったのはショックです。いま、あるのは過去10年間に建った家や建物ですから、地域的な特徴がありません。都内や近郊でよく見るハウスメーカー風の家ばかりになりました。ヴァナキュラーなものがすべて消え失せ、どこにでもありそうな家がヘリコプターで吊り下げられて、土地にポン!と置かれたようです。そうした家だらけですから、「ここは一体どこだ?」と感じます。
それに加えて、地面そのものが変わってしまった。かさ上げされ、高台は山を中腹からスパッと切って、平らにしています。土地そのものが虚構的になったのです。そうした土地や街並みを見ていると、ここは僕が生まれ育った町ではないと思う。自分の思い出とうまくくっつかないのです。接続が本当に難しい。
──この10年間、故郷の陸前高田へ東京から通い、撮影を続けてきました。故郷の変化を継続的に目にしてもそう感じますか。
そうですね。むしろ震災直後、がれきが地面を覆っていた時期の方がいろいろなことを思い出すことができた。当時の方が、まだしも過去との繋がりが見出せました。
──津波で失われた実家はどうなりましたか。
気仙町の実家は震災発生当時、姉が新築したばかりで母と一緒に住んでいました。築1年も経たないうちに流されてしまい、姉は別の場所に住んでいます。実家の土地は近くのかさ上げ地に換地され、いまは土地を前に呆然としている感じです。最近、周りの人が少しだけハッピーになれたり、充実した時間が過ごせたりするような何かをそこにつくれないかと考えています。定規で引いたような道路や橋が目について、魅力がない場所になってしまったのですが。

──震災後に刊行した畠山さんの写真集「気仙川」(2012年)によると、2000年頃から発表を前提とせずに故郷の写真を撮っていたとあります。なぜ撮影を始めたのですか。
そこにある物事が朽ちていく、寂れていく、一種の寂寥感がありました。ベビーブーム後の昭和30年代の陸前高田は人が多く、その活気がある時代から僕の記憶は始まっています。当時と照らし合わせると、津波前の気仙町は寂しくて寂しくて仕方がない場所でした。人口が減り、住民はどんどん歳をとり、都会に出た若者は帰ってこない。僕も人のことは言えません。車社会になり、町の様子も変わりました。車を置く必要が生じたために住宅の形状が変わり、通りに面した家並みが揃わなくなってきたのです。昔は江戸時代からの伝統で間口は狭く、奥行きは深い家が多かったのですが、次第に減って、ノスタルジアになりつつありました。そうした特徴的な風景を撮影しておかないと、永遠に失われてしまうと感じたのです。
──「都市と自然」をテーマに、個人的出来事と距離を置いた理知的な作品を手掛けてきました。寂寥感がある故郷は、石灰石鉱山やボタ山、暗渠など、作品化した撮影対象と重なる部分はあったのでしょうか。
あまりないですね。写真を始めた時からずっと僕が心がけてきのは「驚き」です。驚きは物事を考えさせる最初の一撃になりますから。震災前は、見た瞬間の驚きがなければ写真は価値がないと考えていました。いまは少し違います。写真には最初の驚きだけではなく、さまざまな価値があり、時間が経ってから感じられる驚きもある。
震災後に陸前高田を撮った作品を発表し始めると、作風が変わったと言う人や、以前と違うパーソナルな世界へ行ってしまったと見る人もいました。はたから見ると随分変わって見えるでしょうし、自分でもそう思います。制作に向かう意識は持続しているので、分裂しているとは思いませんが。

2:この10年を振り返り、どのような仕事や姿勢で震災と向き合ってきたと思いますか?
震災でつらい目にあった方は大勢います。いまもつらい人がたくさんいて、故郷に帰りたいのに帰れない、本当に帰りたいのか自問しても答えが出ない方もいる。この10年間はメディアを含め、そうした人々を慰めたり、「明日はもっと良くなる」と励ましたりする言葉をたくさん聞いてきました。僕も震災後、ニューヨークの知人が電話をかけてきて「明日は絶対に良いことがあるから」と言ってくれた時は、嬉しくて泣いてしまいました。ただ僕がいるのは、傷ついた人に慰めの言葉を掛けられる場所ではありません。そもそも、どんなポジションに立って行動すればいいのか、いまでもよくわからないのです。
それは簡単に言えば「私は被災者なのか、それとも励ます側なのか」ということです。この10年間、わからないまま陸前高田の撮影を続けてきました。唯一理由があるとすれば、あの土地に生まれ育った記憶と意識だけです。写真を撮るのは、被災した人を励ますためでも、慰めるためでも、社会へ向けたメッセージでもない。被災者とか当事者とか外部者とかにカテゴライズされない、「誰か」のために続けてきたのだと思います。
震災後、絆やコミュニケーションの創出を目指したり、「笑顔を取り戻す」と銘打ったりした作品が被災地に多く出現しました。なぜアートを使い、人を元気にしなければいけないのか僕にはわからない。アーティストは例外的なものや特異な事象、もしくは単にヘンなものでもいい、人を驚かせたり、考えさせたりする表現を差し出すべきだと思う。それはテレビやネットで交わされるような耳触りが良い言葉の外側にあるものです。 僕は余りにもアートを過大評価しすぎているのかもしれません。ただ、これまで「見て良かった」と思えた作品は、「みんなの笑顔」を目的につくられたものとまるで違うのは確かです。この10年間はアートだけでなく、文化全般や政治に境界がなくなり、どろりと融解して不定形になったと感じています。その原因に震災があるかどうかはわかりませんが。

3:震災以前といま、考えていること/していることに決定的な違いはありますか。
震災後、デジタルカメラを使うようになった。フィルムと印画紙の供給が不安定になり、世の中もフィルムの仕事を必要としなくなったからです。その前の2005年前後、コダックの工場が次々と閉鎖されたのが決定的で、以後モダンフォトグラフィの歴史は終わったと言わざるを得ません。見る人はデジタルでもアナログでも気にしないかもしれませんが、つくり手からすればカメラが違い、操作が違い、プロセスもまったく異なります。でも出来上がりの外見はそっくりだし、デジタルの方が簡単で便利です。ただ僕は素材から発想するタイプなので、電子信号のデジタルになかなか移れませんでした。2010年ごろから印刷所に作品を持っていくと「紙焼きですか」と渋い顔をされ、紙焼きの扱いに慣れた職人も減ってきたので、デジタルカメラも使うようになりました。でも、これは震災と関係ない話ですね。
──陸前高田での撮影はデジタルカメラですか。
使っていません。撮影を始めた時からフィルムだったし、変えるつもりはありません。 デジタル写真は成り立ちが違うのです。仕上がりのルックスは同じでも、フィルムの写真とは成立のプロセスや素材が全く違う。僕が大切に考えているモダンフォトグラフィの歴史は、素材との格闘の中から出来上がったものです。その素材が使われない写真は、一見同じでも、その歴史に組み込むことができません。これは僕特有の考え方かもしれないけれど。デジタルカメラを使うのは、例えば依頼された仕事で印刷が前提になっている場合です。
昨年の夏、市役所から依頼されて、気仙中学校や旧道の駅など4カ所の震災遺構を撮影しました。今後、市は公開を前提に保存整備を行うそうですが、撮影時は建物内部にびっしりと土が詰まり、10年前のままでした。この時はデジタルカメラで撮影しました。最近、インクジェットプリントを使って15部だけ震災遺構の写真を収めた自家版の本(「陸前高田市東日本大震災遺構」Ⅰ、Ⅱ)をつくりました。こういう場合、確かにデジタルは便利です。ただ僕は暗室で育ってきたので、やはり紙にプリントして見たいのです。

4:震災後、自分は変わったと思いますか?
世の中が変わった。変わったというのは、皆が信じて来た考えや価値観が相対化されたために、例えばアートなら美術史を基準に考え、作品を判定するシステムが回らなくなった。若い世代は権威に対する感度が鋭くなり、すぐに欺瞞を感じ取って、体制を崩しにかかる傾向が強まりました。それはいいことです。でも、まとまりがない世界になりました。自分はそれほど変わっていないと思います。
5:これからの10年、何をしていくと思いますか?
まったくわかりません。一つ言えるとしたら、人間以外のものを、もう少し気にかけていきたいと思います。
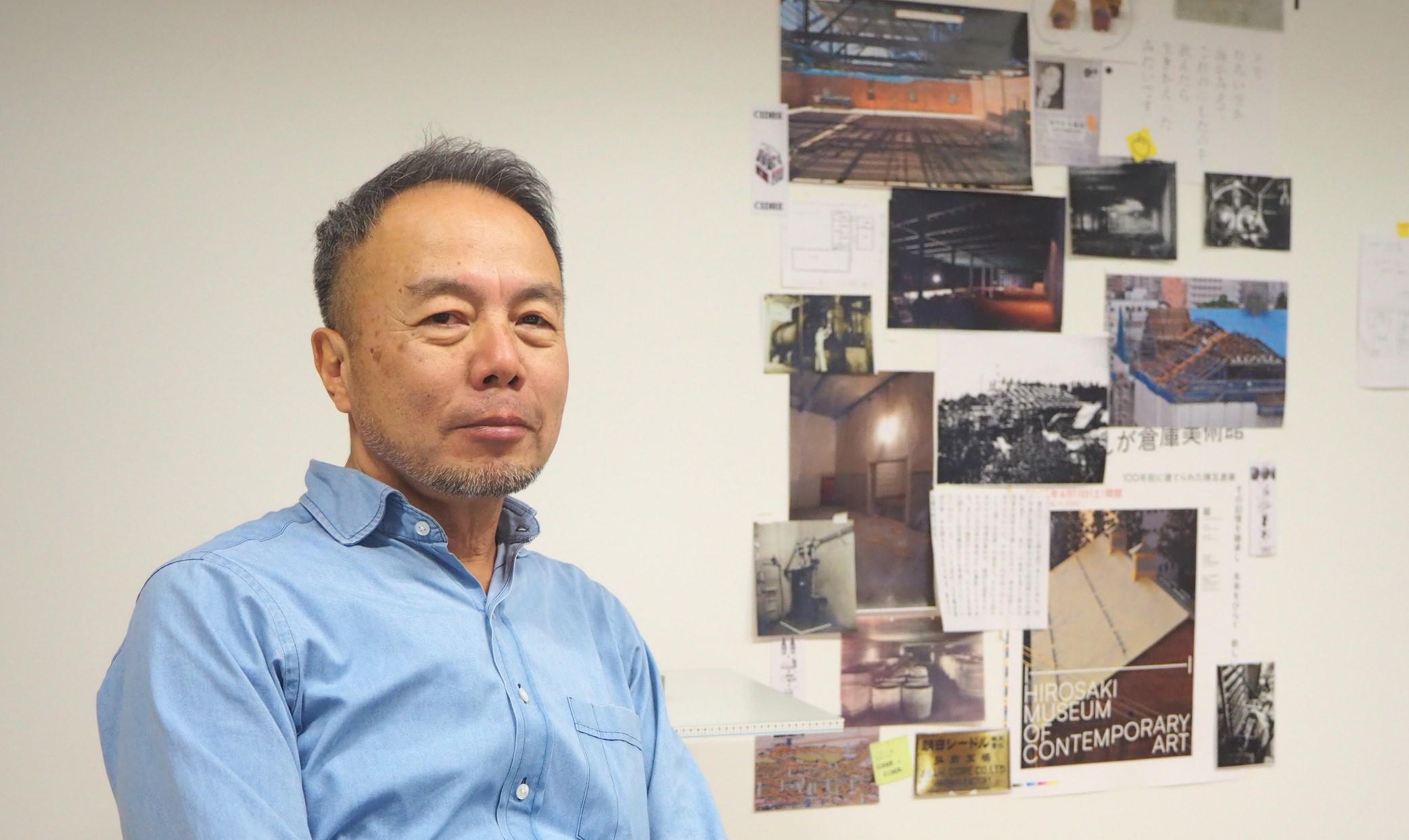
畠山直哉
1958年岩手県陸前高田市生まれ。筑波大学芸術専門学群にて大辻清司に師事。1984年に同大学院芸術研究科修士課程修了。以降東京を拠点に活動を行い、自然・都市・写真のかかわり合いに主眼をおいた、一連の作品を制作。国内外の数々の個展・グループ展に参加。作品は以下などのパブリック・コレクションに多数収蔵されている。国立国際美術館(大阪)、東京国立近代美術館、東京都写真美術館、ヒューストン美術館、イェール大学アートギャラリー(ニューヘブン)、スイス写真財団(ヴィンタートゥーア)、ヨーロッパ写真館(パリ)、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館(ロンドン)。2011年10月、東京都現代美術館での個展「ナチュラル・ストーリーズ」で震災前・後の陸前高田の風景作品を初めて発表し、その後も写真集「気仙川」、「陸前高田 2011-2014」(2015)、せんだいメディアテークでの個展「まっぷたつの風景」(2016~17)と故郷と関わる制作活動を行ってきた。



